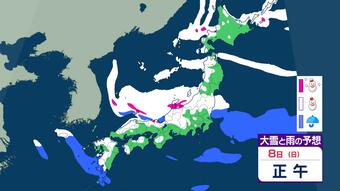不登校の小中学生は過去最多の約24万5千人に上っています(2021年度文科省調査)。学校に行かなくても、それぞれの子どもが自分のペースで学び続けられる新たな“居場所”づくりが急がれます。
中学時代に学校の雰囲気になじめず不登校になったものの、民間のフリースクールに通ったことをきっかけに勉強の楽しさに気づき、この春東京大学に入学した東京大学1年生・磯田大翔さん(19)に話を聞きました。
(TBSテレビ報道局社会部厚労省キャップ:岡村仁美)
■「いろいろなスタイルの勉強方法を選べたのがよかった」
ー不登校になった理由はなんだったのでしょうか
僕が不登校になったのは中学1年生の夏頃でした。受験をして入った国立大付属の中学校でしたが、具体的に何かが嫌だったから行かなくなったのではありません。学校の雰囲気だったり空気感が合わなかったのだと思います。学校に行かなくなってからは部屋にひきこもり何もせずに寝ていたり、夜通しゲームをしたりという生活を送っていました。
高校受験を意識するようになった中学3年生の頃、母親の紹介で熊本学習支援センター(民間のフリースクール)に通うようになりました。

ー学校とは何が違いましたか
自由なところが一番良いと思っていて。自分で勉強したいなと思ったときに、みんなが遊んでいる楽しい空気感を味わいながら勉強したり、本当に集中したいときは集中できる場所もありますし。いろいろなスタイルの勉強方法を選べるのが良かったと思っています。僕はルービックキューブでよく遊んでいました。自由にできるのでやらされているということもなく、自分の興味に従って勉強することができました。

磯田さんはフリースクールに通い始めたことをきっかけに勉強を再開し、熊本県内の私立高校に進学。高校時代にも一時不登校となりましたが、高校が図書館へ登校することを認めていたこともあり、自分のペースで勉強を続け、この春東大に現役合格しました。現在は教養学部理科一類の1年生で、最先端の研究がされている場所で勉強できることにわくわくしていると言います。
■「時代は変わっているのに学校が変わらない」
磯田さんが通っていたフリースクールの代表は不登校の子どもが増えていることについて、「学校という集団生活が合わない子どもが増えてきている」と指摘します。