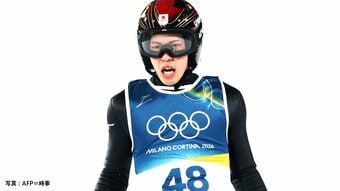3%インフレは行き過ぎ
今後タイムラグを伴いながらも、名目賃金が少しでも上昇することを期待していますが、それでも物価上昇率の大きさを考えると、実質賃金マイナス脱却するには時間がかかりそうです。
実質賃金算出に使った物価変動率は、先に述べたように4月は4.1%の上昇でした。消費者物価指数(総合)も4月は3.5%の上昇でした。30年ぶりの賃上げと言っても、ベア2%では、今の物価上昇には全く追いついていないのです。
日銀は、23年度後半には物価上昇が2%を下回るレベルになるとして、今の高い物価上昇を静観しています。3%以上の物価上昇は、国民にとって、とても「物価が安定した状態」とは言えないのに、『放置プレー』状態です。インフレをさらに加速させる円安に歯止めぐらいかける時期に来ているように思います。
消費と景気に急ブレーキの恐れも
13か月も実質所得が減り続ければ、家計の財布の紐が固くなるのは当然です。総務省の家計調査によれば、4月の消費支出は物価上昇を除いた実質で前年同月比4.4%もの大幅な減少となりました。
コロナ禍からの経済活動の正常化を受けて、外食、外出、旅行関連支出は、軒並み2ケタのプラスになっていますが、身近に節約できる食品が1.1%落ち込んだのを始め、教育や通信などもマイナスとなっています。実質消費支出は、22年の11月以来、電気・ガス代に対する補助金支給が始まった2月を除き、マイナスが続いています。
要は、コロナ禍の消費自粛からの反動・ベントアップ需要が消費と景気を支えている構図です。だとすれば、反動消費(リベンジ消費)が一巡し、コロナ禍で使わなかった貯蓄が入っていた、今のお財布が空になってしまえば、消費に急ブレーキがかかりかねません。
岸田政権が目指す経済の好循環は、消費や景気の失速を招かないことが大前提のはずです。ボーナス増額や手当支給などあらゆる手段で、人々が今後も賃上げが続くと確信できるようにすること、そして、物価の上昇を適度なレベルにとどめることが、何より必要なことだと思います。負担増の話など、今は、もってのほかです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)