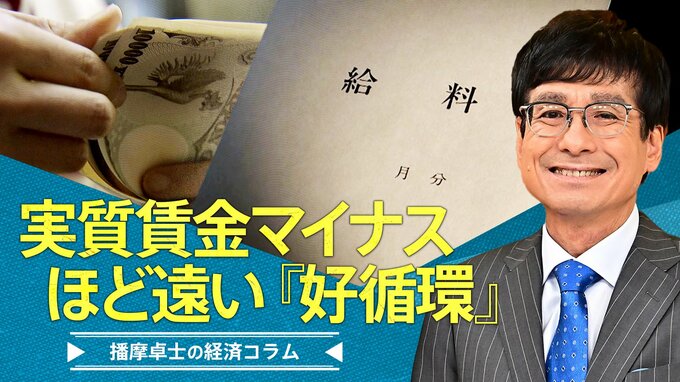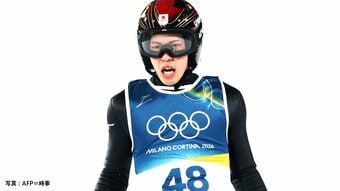がっかりさせられる数字でした。物価変動を考慮した実質賃金が、年度が替わった4月も、前年比3.0%減と、13か月連続でマイナスになったのです。
新年度も実質賃金マイナス幅拡大
厚生労働省が発表した4月の毎月勤労統計によれば、従業員5人以上の事業所の1人あたりの現金給与総額は28万5176円と前年同月比1.0%の増加でした。
しかし、実質賃金の算出に用いる物価(持ち家の家賃換算分を除いたもの)が4.1%もの上昇となったことから、物価変動を考慮した実質賃金は前年同月比で3.0%もの減少となりました。
実質賃金は、22年4月以来一貫してマイナスで、2022年度通年では1.8%の減少でした。しかし、23年の春闘で30年ぶりという高い水準の賃上げ回答が相次いだことから、新年度入りした4月に、実質賃金が改善することが、大いに期待されていたのです。
しかし、ふたを開けてみれば、実質賃金の減少は3月の2.3%減から3.0%減へ、さらに拡大する結果でした。
春闘では30年ぶりの賃上げが実現
連合の集計によれば、23年の春季労使交渉は、正社員の賃上げ率3.7%で妥結しています。一方、4月の名目賃金である現金給与総額が1.0%、その内の所定内給与が1.1%しか増えておらず、春闘の『成果』とは大きな開きがあります。
その理由はいくつもあります。まず、3.7%の賃上げと言っても定期昇給を含んだ数字です。定期昇給はマクロ的には賃上げには当たらず、純粋な賃上げであるベースアップ(ベア)は2%程度にすぎません。
また、タイムラグも考えられます。妥結が遅れたり、未だ交渉中だったりする企業では、給与改定が4月には間に合わず、実際の賃上げが5月以降に繰り延べられるからです。5月、6月に名目賃金がどこまで上がっていくかが注目です。
さらに、そもそも労働組合のナショナルセンターである連合の集計対象になっていない企業では、それほど大きな賃上げが実現していない可能性もあるでしょう。