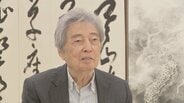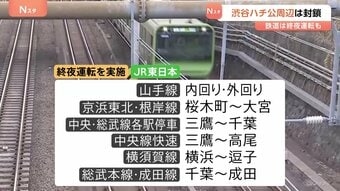「92年後の無料化」に説得性はあるか
2115年は92年後です。「92年後に無料化します」なんて、政策としての説得性があるでしょうか。「租借地の100年後の返還」じゃあるまいし、予見し得る将来とは、とても言えません。
普通に考えれば、高速道路のメインテナンスは、今後も恒常的に必要ですし、新たな高速道路整備も続くのであれば、有料化は半永久的に続くと考える方が自然でしょう。「無駄な高速道路は作らない仕組み」とか、「無料化に向けた取り組み行程表」と言った具体的な政策は全く示されず、50年先延ばしを決めただけでは、信じろという方が無理です。
地方には新直轄方式の「無料区間」が続々
こうして高速道路の有料化が半永久的に続く一方で、地方では「新直轄方式」による「無料区間」の高速道路が続々と開通しています。「新直轄方式」とは、2005年に道路公団が民営化された際に、生み出された仕組みで、民営会社ではとても採算がとれない区間については、国と地方自治体の直轄事業として、要は税金で高速道路が整備されているのです。
結局のところ、人がたくさん使う高速道路は、高速道路会社が建設して、22世紀まで高い料金を負担しなければならないのに、人が大して乗らない高速道路は料金無料で、どんどんできていくという構図です。不公平感を持つ人がいて当然です。
「92年後の無料化」より、料金引き下げの具体化を
安全のために、高速道路の維持管理に今後も費用が必要なことはわかります。高速道路の便益を享受する利用者が、料金の形で一定の負担をすることは、財政状況を考えても、致し方ないことかもしれません。それでも、今のままで良いとは、とても思えません。
何と言っても、すべての料金収入をプールにして、建設費や修理・更新費、その他の施設整備費に充てるという「どんぶり勘定」では、いつまで経っても、無料化どころか、料金引き下げの目処もわからず、利用者の納得は得られません。
確かに道路はつながっているので、区間ごとに厳格なコストを算定することは難しいかもしれませんが、それでも50年以上料金を取り続け、とっくに建設費の償却も終わって、メインテナンス費だけになっている区間と、昨日今日、完成したばかりの区間の間で、料金に一定の差をつけることは可能なはずです。
また、週末のETC割引のように個人旅行向けなど各種の割引制度もより拡充して、国際的にも高いと言われる高速料金を少しでも引き下げる努力が必要です。ETCの普及で多様な料金体系の適用が可能になってきているはずです。
利用者が「安全な高速道路維持のため」と納得して料金を負担できるよう、具体的な引き下げ努力を示していくことこそが、持続可能な制度の鍵になるのではないでしょうか。