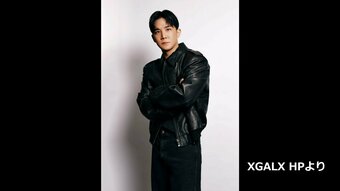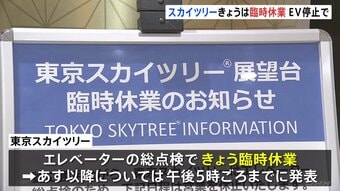大きく後退した植田総裁の「見直し姿勢」
植田総裁自身、すでに「イールドカーブ・コントロールの維持は適切」と述べていて、当初の期待とは裏腹に、植田日銀の政策見直しは大きく遠のいています。
当初、異次元緩和の副作用を受けて政策修正に言及していた植田総裁が、ここまで慎重になっているのは、3月以降、アメリカの銀行破綻が相次ぎ、世界的な金融不安が高まっていることが大きな要因だと思います。
それに加えて、決定会合の参加メンバーの空気感や、日銀の事務方による説得、さらにはアベノミクス修正に対する政治力学などを考慮したからでしょう。
確かに、ようやく出た「インフレ2%実現」の芽を今は摘みたくないという気持ちはよくわかりますが、それでも大きな政策修正は、人事や体制が変わった直後にやらなければ、後ずれすればするほどやりにくくなってしまいます。なぜなら、それまで変えなかった理由もあわせて問われることになってしまうからです。
アメリカの利下げ局面では、政策修正は困難か
その上、金融政策をめぐる国際的な環境が大きく変わりつつあります。これまではアメリカは利上げ一辺倒の局面でしたが、今後は「利上げ打ち止め」、さらには「利下げ」が視野に入ってきます。
日銀が今後行う政策見直しは「引き締め」方向ですから、欧米が利上げ局面なら「やりやすい」のですが、利下げ局面では逆方向になってしまい、一気に円高を招きかねないので、とても「やりにくい」のです。ベストなタイミングはすでに過ぎ去ってしまいました。
今後、日銀が政策変更できるのは、アメリカが利下げした結果、再び景気が上向いて、次の利上げ局面に入った時期ということになり、どんなに早くても24年半ば以降になってしまうでしょう。
植田総裁の任期は5年です。滑り出しは、現状維持の「安全運転」が好感されても、「安全運転」だけでは、何も変えられないまま終わってしまうリスクもあるのではないでしょうか。初の経済学者出身として注目される植田総裁が、手遅れにならないうちに、「植田カラー」をどう打ち出すかが焦点になります。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)