■多可町の教職員たちの感想
2019年夏、逝去の4か月前に行われた森田洋司の講演を兵庫県多可町の教職員たちは、どう聴いたのか。

(写真提供:多可町教育委員会)
受講者アンケートには、教員たちの率直な思いが綴られていた。
男性教員・30代:
“いじめ防止対策推進法”の内容、読んだか!?の問いには、背筋の伸びる思いでした。読みます。
女性教員・年代不明:
基づくものは何であるか。法について学んでいなかった。
女性教員・30代:
自分の認識や知識の甘さを痛感しました。
男性教員・40代:
教師たちが“共通理解”ではなく、“共通の認識”をしておくことが最も必要である。
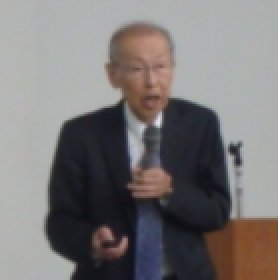
(写真提供:多可町教育委員会)
法律にある「いじめの定義」で全ての教職員が“共通の認識”を持つこと。そしてその定義に基づき認知すること。それこそが、“いじめの芽”を摘むための第一歩となる。子どもたちの尊厳を傷つける全ての行為を常にウォッチする姿勢が、求められている。
資料:「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
におけるいじめの定義の変遷
*2015(H27)年度以前の調査名称は「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」
【1985(S60)年度調査~1993(H5)年度調査までの定義】
いじめを「①自分より弱いものに対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないものとする。」として調査。
【1994(H6)年度調査~2005(H17)年度調査の定義】
この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。
なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
【2006(H18)年度調査~2012(H24)年度調査の定義】
本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
(注1)「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、
いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視することである。
(注2)「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、
同じ学校・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や
集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者
を指す。
(注3)「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的に
かかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与える
ものも含む。
(注4)「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり
隠されたりすることなどを意味する。
(注5)けんか等を除く。
【2013(H25)年度調査からの定義】
※ いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度から以下のとおり定義されている。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)。(以下「法」という。)第2条第1項)をいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
(注1)個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的
に行うことなく、法が制定された趣旨を十分踏まえ、行為の対象と
なった者の立場に立って行うこと。特に、いじめには多様な態様が
あることに鑑み、いじめに該当するか否かの判断に当たり、定義の
うち「心身の苦痛を感じているもの」との部分が限定して解釈され
ることのないようにすること(例えば、いじめられていても、本人
がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表
情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。)。
(注2)「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や
部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっ
ている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒が有する何らか
の人的関係を指す。
(注3)「物理的な影響を与える行為」には、身体的な影響を与える行為の
ほか、金品をたかったり、物を隠したり、嫌なことを無理矢理させ
たりすることなども含まれる。
(注4)「行為」には、「仲間外れ」や「無視」など直接的に関わるもの
ではないが心理的な圧迫等で相手に苦痛を与えるものも含まれる。
(注5)けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも当事者
となった児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。
※ 2016(H28)年度より(注5)を以下のとおり変更。
(注5)けんかやふざけ合い、暴力行為等についても、背景にある事情の
調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当する
か否かを判断する。
執筆者:TBSテレビ「news23」編集長 川上敬二郎














