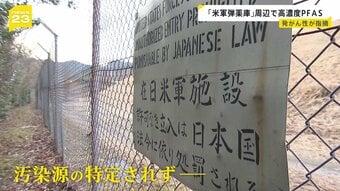なぜメッセージは「炎上」するのか? そのメカニズムと回避策
野村:想いは素晴らしいのに、表現が間違っていた結果、炎上してしまうケースは確かに目にしますね。
辻:よかれと思ってやったのに炎上すると、「もう怖くてこのテーマには触れないでおこう」となってしまう。しかし、他社の炎上事例を分析すると、どこに炎上の種があったのかは、かなりクリアに分析できます。未然に防ぐことは十分に可能なのです。
野村:具体的には、どのような点が炎上の火種になるのでしょうか。
辻:それぞれの社会課題の領域には、独自のコミュニティや言葉遣いが存在します。「このテーマでこの言葉を選ぶと、意図しないニュアンスで受け取られる」といったハイコンテクストな表現が無数にあるのです。例えば、「障害は個性だ」という表現は、時として暴力的になり得ます。誰が言うかにもよりますが、その人の痛みをなかったことにしてしまう可能性があるからです。過去には、こうした表現に関連するコピーが炎上した事例もあります。
一方で、日本では「炎上」と一括りにされがちですが、中には建設的な「議論」になっているものや、当然「賛否」が分かれるものもあります。
野村:そうですね。明らかに不適切なものに対する指摘もあれば、言いがかりのようなケースまで様々です。
辻:意図的に火をつけようとする「放火」のようなケースもありますね。だからこそ、私たちは「この企画、このメッセージは誰のために出すものなのか」という原点を、事前にクライアントとかなり密にコミュニケーションを取ります。
例えば、12月にある「障害者週間」に向けた施策なら、中心となるのは障害のある当事者の方々です。その方々が抱える課題や見えている景色を広く届けることが目的になります。もちろん、障害のない方から様々な意見が出る可能性はありますが、あくまで「この企画は誰のためにやるのか」を明確にすることが重要です。この軸がずれると、炎上が直接株価に影響することさえあります。