11月29日、青森県が初めて感染確認を発表した顎口虫症(がっこうちゅうしょう)

寄生虫が皮膚の下に入り込み、かゆみや腫れを引き起こします。この寄生虫が、どうやって皮膚の下に入り込むのか、なぜ開発が進んだ現代に大量発生したのかを専門家に聞きました。
こちらが寄生虫の一種、「顎口虫(がっこうちゅう)」の成虫です。

イタチに寄生した場合、成虫になるとされています。ただ、人間に寄生した場合は、幼虫のまま皮下組織に移動、皮膚にかゆみや腫れの症状がなど出る顎口虫症を引き起こします。寄生虫を研究している北里大学獣医学部の筏井宏実(いかだい・ひろみ)准教授です。
※北里大学 獣医学部獣医寄生虫学研究室 筏井宏実 准教授
「下から動いたのか、上から下に動いたのかわからないが、虫が動いた跡が、このようになる」


今回、この顎口虫症と似た症状が確認されたのは、上十三保健所管内と八戸市内の約130人。その多くが、シラウオを加熱せず食べていました。筏井准教授によりますと、シラウオの中にいた顎口虫の幼虫が人の胃や腸を突き破って筋肉を通り皮下組織まで移動したとみられるということです。

※筏井准教授「本来この寄生虫は体の中を動くという特徴があります。人が食べると、おそらく消化管内から幼虫が、今回だとシラウオから出て、体の中を動いてさまよい続ける」
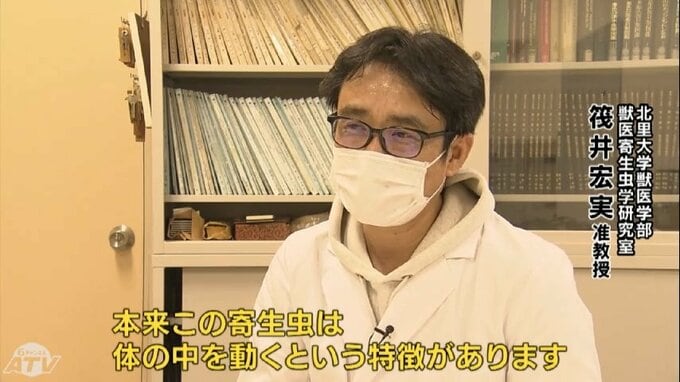
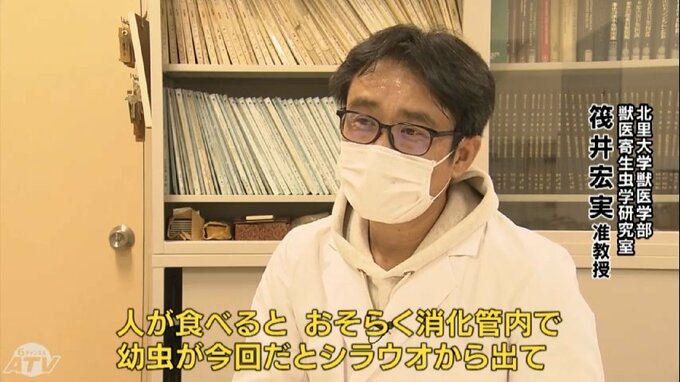
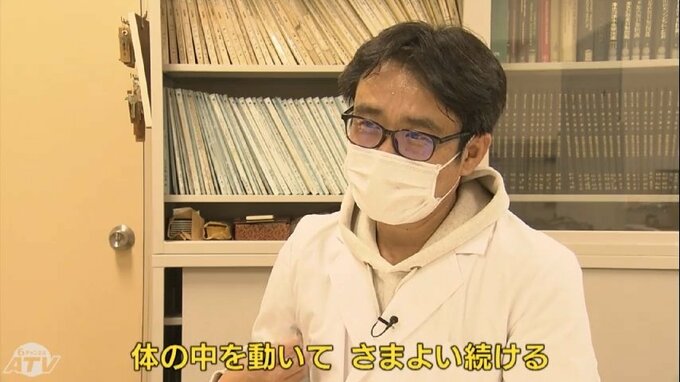
1990年代の北里大学獣医学部の調査では、青森県内のシラウオから顎口虫は見つかりませんでした。それでは、なぜ開発が進んだ現代、そして青森県のシラウオで大量に発生したのか。筏井准教授は、その要因について次のように考えます。
















