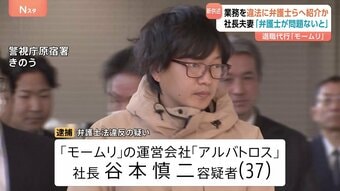洋上風力は再エネ拡大の切り札
日本は、脱炭素社会実現に向けて2040年度には再生可能エネルギーによる電源を全体の4~5割にまで引き上げることを目指しています。今の割合の倍以上です。風力発電に限れば、今の1%を、4~8%に引き上げる計画です。
これまで再生エネルギーでは太陽光がリード役を担ってきました。しかし、平地が少ない日本で、これ以上のメガソーラー建設には限界がありますし、陸上風力も同様に適地が次第に少なくなっています。洋上風力には、漁業権の問題はあるものの、騒音や日照の問題は少なく、風の適地も見つけやすいことから、文字通り、今後の再エネ拡大の「切り札」とされています。脱炭素の観点からは、簡単に洋上風力をあきらめるわけにはいきません。
「再エネ賦課金」によるコスト負担は限界に
入札制度の見直しなどは必要だとしても、洋上風力発電のコストが大きく増大していることに変わりありません。制度上の工夫を行って、収支計画を立てやすくするとしても、コストの増大は、最後は誰かが負担しなくてはなりません。
現在は、太陽光や風力発電で作られた電気はまだまだコストが高いので、一定期間、電力会社が固定価格で再エネによる電気を買い取る決まりになっています。そのコストは、消費者が電気料金に上乗せされる「再エネ賦課金」を支払うことで負担しています。
当初は少額だった再エネ賦課金も、再エネの比率が高まるごとに値上がりし、2025年度は1キロワット時当たり3.98円と、標準家庭では月1500円程度に達しています。物価高対策として再エネ賦課金の廃止を訴える政党も出てきており、再エネ賦課金の引き上げによって再生エネルギーの普及・拡大を図るという政策も、徐々に限界が見え始めています。
この上、洋上風力のコストが上がり、その比率も高まるのだとしたら、なおさらです。消費者が一律に負担する再エネ賦課金制度を、どのように運用し、変えていくのかも、今後の大きな課題です。
地元自治体からは「撤退とさえ言えばいいのか。あまりに無責任だ」との声まで上がると共に、「三菱商事さえ撤退に追い込まれるほど、洋上風力は厳しい」との見方も広がるほど、衝撃を与えた撤退劇。政府肝いりの洋上発電からの、いわば本命企業の撤退は、日本の再生エネルギー戦略に様々な課題を投げかけています。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)