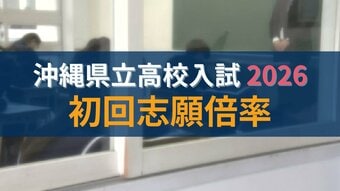生徒の “自治組織” である生徒会は一般に、学校生活の向上のために問題の解決や行事の計画・運営などを担う。
執行部の役員がその活動の中心となり、全校生徒が生徒会の一員として投票や議論に参加する権利がある一方で、生徒からの積極的な関わりがなければ、形骸化した存在にもなりかねない。

大城さんは、生徒総会で時間割の改善を提案する際、教員との公開質疑や反対意見への答弁を取り入れた。「下校時刻が変わることで帰りのバスに間に合わなくなるのでは」といった懸念には、バスの時刻表など具体的な資料を提示し、問題ないことを丁寧に説明した。
さらに議案の承認方法を拍手から起立制にすることで、生徒それぞれが明確な賛否を表明できるようになった。
「これまでの過程をオープンにして、なるべく多くの人が理解して納得できるような形にしました。反対する人ももちろんいましたが、拍手では誰が賛成で誰が反対か分からないので、これは起立制にしたからこそわかること。ただ、ほとんどの生徒が賛成していたので、会はスムーズに行きました」
改革を通じて、これまで形式的だった生徒総会は「生徒一人ひとりが自分の頭で考え、意思表示する場」へと進化した。
生徒総会での承認を経て、生徒会は通常の日課の昼休み後に5分間の移動時間を追加する「新日課」を学校へ提案した。校長・教頭・学年主任らと会議を開き、教員へも直接説明をしたうえで、職員会議が開かれ、提案は承認された。