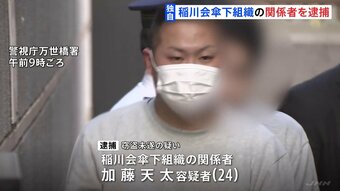世間話と問診は別物だけど…最大のデメリットと未来像

診療において最も重視されるべき問診が、日本の診療報酬制度では正当に評価されていない――これは生坂先生が長年感じてきた大きな課題だ。「問診をどれだけ丁寧にしても、報酬にはほとんど反映されません。問診単独の評価が存在しないのが現状です」と語る。
「問診は全ての医師が行う基本。診断の7割は問診で決まるといわれています。このスキルを磨くことで無駄な検査や過剰な専門治療を避け、医療費の抑制にもつながる」。とりわけ超高齢社会を迎えた日本では、効率的で持続可能な医療体制の鍵になると指摘する。
しかし、問診の評価は難しい。「沈黙」などの高度な技法が含まれるため、表面的な時間や行為では測れないからだ。生坂先生は、「沈黙は、ただ喋らないこととは違う」と語る。「沈黙の時間を意図的に作ることで、患者に考えさせ、気づかせる。そのタイミングを見極めて使うのは非常に効果的であり、問診の中でも重要な技術の1つです」と強調する。
「ある上司に“時間をかけるから診断できるんじゃないか”と言われたことがあります。しかし、たっぷり時間をかけて問診したからといって誰もが正解にたどり着けるわけではない」とも。
患者ごとに適した聞き方は異なり、それを瞬時に見極めるには豊富な経験と技術が必要だ。「今後、AIなどの技術を活用して問診の質を評価できる仕組みが生まれれば、総合診療医の価値も正当に見直されるはず」と期待を寄せる。
そのうえで、日本の医療制度の持続性についても言及。「国民皆保険制度という素晴らしい仕組みを持つ日本ですが、医療費と介護費の増大は深刻な課題です。ワンストップで診られる総合診療医の存在が、制度維持の鍵になると私は考えています」。
「医師から見ても国民から見ても、総合診療医の役割はまだベールに包まれている。しかし、この分野に対する期待が高まれば、現行の制度を維持しつつ、さらに良い方向へ進めるはずです」と前を向く。
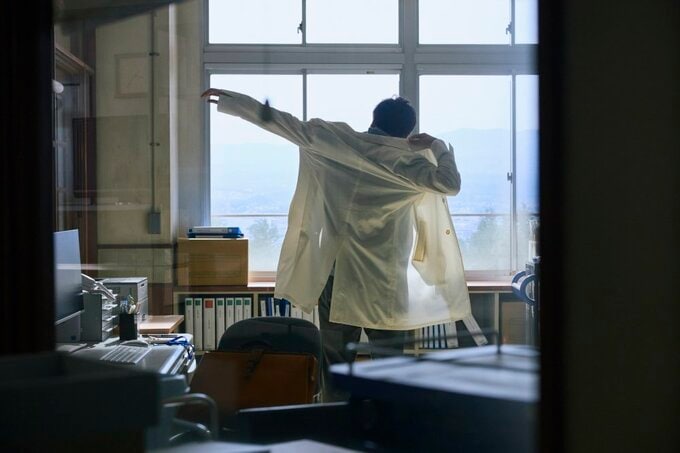
「監修を務めたドラマを通して、総合診療医の存在が広く知られることを願っています。知ってもらうことで、医療制度そのものが良くなるきっかけになると信じています」と生坂先生。
制度としてはまだ若く、医師数も限られる総合診療医。しかし、生坂先生の言葉からは、その存在が今後の国内医療の持続可能性に深く関わっていくことが読み取れる。患者の最初の相談相手として、また限られた医療資源を有効に活用するオールマイティーな助っ人として、総合診療医への理解と関心が、今後さらに高まっていくことが期待される。