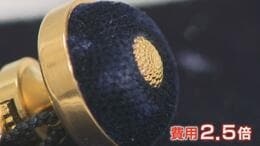「体がだるいけど何科を受診すればいいのか分からない」「通院しても一向に改善しない」――そんな悩みに、誰しも一度は直面したことがあるのではないだろうか。医療の進歩とともに診療科が細分化される中、戸惑う人も少なくない。
その声に応える存在として近年注目されているのが、「総合診療医」だ。臓器や年齢、性別を問わず、“人を診る”医師として2018年に制度化され、「19番目の専門医領域」として正式に発足したこの診療科は、まだ多くの人にとってなじみが薄い。
その実像を正面から描く日曜劇場『19番目のカルテ』(TBS系)で、総合診療科の監修を務めるのが、生坂政臣医師。千葉大学医学部附属病院の総合診療科を立ち上げ、現在は一般社団法人日本専門医機構で総合診療領域の担当委員長として制度運営にも関わっている。「人を診る医師」とは何か。現場と制度、両面からこの分野を見続けてきた第一人者が語る、その真価とは。
知られざる“19番目の専門医”とは?
内科、整形外科、眼科、皮膚科……病院の診療科は臓器や症状ごとに細かく分かれ、医師も各専門に特化していく。現在、制度上の「専門医」は18の基本診療領域に分類されているが、2018年、新たに19番目の領域として加わったのが「総合診療科」だ。
制度が始まってから7年目を迎えるが、全国の専門医数は今も1000人未満と少なく、都道府県によっては医療圏ごとにすら配置されていない現状がある。
生坂先生は、制度創設の経緯について「日本専門医機構が総合診療専門医の養成に着手したのは2018年からですが、実はその前の2013年、厚生労働省が総合診療専門医を専門医として19番目に位置付けたのが始まりでした」と振り返る。
「新しい領域ということもあって、専門医全体の中で総合診療に進む人の割合はまだわずか3%ほど。毎年およそ1万人の医師が卒業し専門医を目指しますが、その中で総合診療医は約300人しか養成されていないのが現状です」と実情を明かす。
この診療科は、1つの臓器や年齢、性別に縛られず、患者全体を診る姿勢が求められる。「専門がないことが専門なのではないか」と揶揄されることもあると生坂先生は苦笑する。だが、実際には「7つの資質・能力」を明文化しており、そこには包括的統合アプローチや地域志向、患者中心の医療、公益性などが含まれる。
「総合診療医は“十人十色”です」と生坂先生は言う。その理由について、「総合診療医は全ての領域の基本知識を身につけているので、その後の現場のニーズに合わせて分化しやすいんです」と説明する。例えば、小児科医がいない地域に派遣された場合、最も不足している小児医療を中心に診療を行う。大半のよくある健康問題は総合診療医が対応できるため、専門的な判断が必要とされるケースのみを小児科専門医に紹介する。「その地域の住民から見ると、総合診療医は“小児科医”に見えるわけです」と語る。
また、大学病院に設置された総合診療科では、診断がつかない患者の“受け皿”として機能することもある。「どこに行っても診断がつかない人が様々な医療機関をさまよっていれば、その方々を受け入れる場所として大学に診断に特化した外来を設置することもあります。これも総合診療の一形態です」。
そのため「町の診療所で働く医師ですか?」という問いにも「イエス」、一方で「大学病院にもいますよね?」にも「イエス」と答えることになるという。「基本知識を習得する3年間を経た後、それぞれの勤務地に応じて不足する診療科を補うように進化する。だからこそ医師像は“十人十色”になるんです」と付け加える。
さらに、「『最後の砦』ともいわれますが、確かにそういう役割もあります。ただ、総合診療医は多くの場合、ファーストコンタクトの医師。地域の診療所などで最初に患者さんに接して、140以上の疾患に対応できる。何でも相談できるかかりつけ医となり、そこから必要に応じて専門医に紹介しています」と話す。
「もちろん大学病院にいて診断が困難な例を診たり、僻地で必要な医療を提供したりもします。足りないものを補える存在、それが総合診療医です。使い勝手がいいという言い方は語弊があるかもしれませんが、それだけ柔軟だということです」。
柔軟性は非常時にも発揮されている。「コロナ禍では感染症専門医や呼吸器内科医だけでは足りなくなりました。その時に総合診療医が助っ人として全国で活躍しました」と生坂先生。「感染症の専門家ではないけれど、基礎的な知識をもとに幅広く対応できる。それが強みです」とも強調する。
日本の医療制度がフリーアクセス、つまり患者が自ら診療科を選ぶ仕組みである点も関係しているという。「自分が何科を受診すればいいか分からない。そんな時にまず相談できる“医療の入り口”になるのが総合診療医です」。