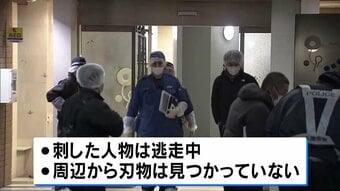3つのレベルのAI故人
AIによる故人の再現をどのように受け止めていくか。本稿では3つのレベルに分けてまとめておきたい。
一つには、コンテンツとしての再現である。歴史上の人物や有名人らが残したデータから写真や動画、あるいは作品を生成することは、より鮮明な歴史資料への好奇心や娯楽的な価値への期待から肯定的に受け入れられる可能性があると考えられる。
二つには、資料やデジタル遺品の加工だ。写真をより鮮明にすること、写真から動画を作るといった、既にあるものを材料とした生成物については、技術的な進歩による新たな選択肢として受容されつつあるとみられる。特に、死別経験者がより肯定的な意向を示していることは、このようなAIの使い方が喪失経験のある人への新たな選択肢になりうることを示唆している。
三つめは、対話やチャット機能など、インタラクティブにやりとりできる形の再生である。こうした対話型のAI故人生成については、歴史上の人物から身近な人物まで、全般的に肯定的な回答は3割未満となった。特に自分の先祖についての希望は1割程度と低く、「対話」機能の導入にあたっては感情的な抵抗感がある可能性が高く、また生成される新たな発言が及ぼす心理的影響や社会的影響も懸念されるだろう。
AIによる故人の再現は、「できてしまう」からといって、すべての技術やサービスが同じように受け入れられるわけではない。技術的な可能性を追求するだけでなく、利用者のニーズと受容度に応じた適切な形態の提供を考えていく必要がある。
注1 姫川榴弾「信長名鑑」太田出版 2019
注2 高木良子「亡き娘と再会する〜韓国のドキュメンタリーを事例に(インタビュー)」中島岳志編「RITA MAGAZINE2 死者とテクノロジー」ミシマ社2025
注3 佐藤啓介. 2022. “死者AIをめぐる倫理のための理論的基盤を考える.” 宗教と倫理 22 (December): 57–70.
<執筆者略歴>
折田 明子(おりた・あきこ)
1998年慶應義塾大学総合政策学部卒業。2000年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。2007年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程単位取得退学。博士(政策・メディア)。
中央大学大学院戦略経営研究科助教、ケネソー州立大学客員講師などを経て、2013年より関東学院大学に講師として着任。2022年から現職。専門は情報社会学、経営情報学。
人間の死後、残されたデジタルデータはどのように扱われるべきか。また、そのデータを用いた「AI故人」の生成にあたっては、どのような可能性と問題があるのか。JST-RISTEX助成プロジェクト「亡き人のAI生成に関するトラスト形成と合意形成」の研究代表者として、社会的な合意形成について調査・研究を行っている。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。