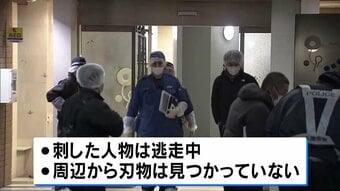歴史上の人物は?
2025年の調査では、歴史上の人物について聞く質問も入れた。
NHK大河ドラマの2023年の主人公徳川家康、2024年の主人公紫式部を挙げて、肖像画やドラマ、マンガ、アニメといった従来の作品としての再現、AI生成による写真や動画といったよりリアルなコンテンツとしての再現、そしてAIによる音声・文字による会話の実現それぞれについて聞いてみたのである。
その結果、肯定的な回答はそれぞれ、従来の作品としては約35%、AI生成のリアルなコンテンツも約31%、AIによる会話の実現は約25%であった。
人物をこちらから指定せず、回答者が自分で過去の偉人を想定した上で答える設問でも、肯定的な回答は「過去の偉人がAIで生成した動画で当時のことを語る」は約35%、「過去の偉人とアプリで会話」は約25%だった。
これらの結果から、歴史上の人物に関してよりリアルな映像やコンテンツとして再現すること自体にはコンテンツとしての価値を感じられる可能性はあること、しかしインタラクティブなやりとりにはまだ慎重である傾向が見えてくる。
心の中で話しかける存在
ところで、愛する人を失ったとき、人はその悲しみにどう向き合うか。20世紀にはその喪失感を乗り越え、故人への執着を手放すことが理想だと考えられてきた。しかし近年では亡くなった人とのつながりを保ち続ける「継続する絆」という考え方が広まりつつある。
日本の社会では、日常的に「死者とともにある」感覚は広く共有されているといえるだろう。仏壇に手を合わせたり、命日に供え物をしたり、ときには心の中で話しかけるという感覚がまさにこの「継続する絆」である。
筆者も欧州の学会に参加した際「この国が好きだった亡き祖母に『おばあちゃん、私もここに来たよ』と話しかけながら来た」と話したところ、「これがあの"継続する絆"か!」と驚かれた。逆に私は、これが驚かれることなのかと驚いた。
しかし、このように心の中で話しかける相手は、生前のそのままの人物ではなく、記憶や思いに基づいて積み上げられた別の存在ともいえる。
亡くなった娘さんとVRで再会した女性にインタビューをされた研究者の高木良子さんは、目の前に再現されるものがむしろ「似ていない」ことが感情移入のきっかけになりうると指摘した(注2)。本人に忠実に再現することは、記憶にある個人像とのズレを明確にしてしまい、違和感につながるのかもしれない。
たとえば、冒頭に挙げたAI美空ひばりの場合、もし姿形を再現せず、歌声の再現だけだったならどうだっただろうか。等身大で再現された姿で、まるで生きていた時間をそのまま共有していたかのように振る舞うことが、心の中の美空ひばり像とは違うという違和感や冒涜されたという感覚につながった可能性はないだろうか。
こうした感覚について、哲学者の佐藤啓介さんは6つの枠組みを示している(注3)。なかでも、故人AIが「私たちが記憶している死者の姿をしつつ、その死者のイメージと異なる言行をする」可能性があることや、そもそも復活させた故人AIは生きている人にとっての「都合のよい死者像」ではないかという指摘は重要だ。