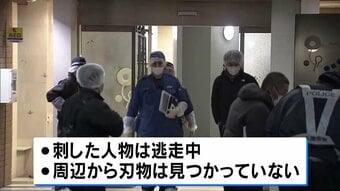故人のAI再現についての意識
亡くなった人をAIで再現するという試みについて、人々の意識はどのように変化してきたのだろうか。
筆者は2022年にデジタル遺品について2つの調査を実施した。一つは著名人の死後のデータに関するもの、もう一つは亡くなった近親者のデータに関するものだ。
それぞれの調査でVRやAIを活用することについて聞く質問を設けたが、いずれにおいても肯定的な反応はほとんど見られなかった。
著名人が亡くなったことを想定した調査(回答者1,200人)では、「VRで故人の姿を再現したい」については、肯定的な回答は6.6%で、否定的な回答は59.6%。「AIを使って音声で故人と会話したい」は肯定的な回答は4.6%で否定的な回答は63.6%だった。わからないとする回答も一定数みられていた。
ただし、特定の人物を想定した場合には傾向がやや異なっていた。たとえば、2020年3月に亡くなったコメディアン・志村けんを想定した群は、8.3%がAIによる音声会話を望んでおり、否定的な回答も49.3%であり、他の人物と比較したときに有意に少なかった。没後も、コンテンツとしてコントが放映され続けていることの影響があるかもしれない。
近年に近親者を亡くした人を対象とした調査(回答者1,303人)では、残されたデータの扱いについて聞いた設問で、「故人の写真を(カラー化などの)加工したい」2.8%、「AIで故人とチャットしたい」1.3%といったように、加工したいという希望はごく少なく、「該当なし」が85%を占めていた。
なお、この調査では残された写真データ等については、半数以上が肯定的に受け止めていたが、なかには「辛すぎてまだ見られない」といった回答もあり、残されたデジタル遺品についてはさまざまな感情があり得ることが示唆された。
しかし、2025年に実施した調査(1,000人対象)では、少し変化が見られた。
昭和を想定した生成写真の例を示した上で、曾祖父母や祖父母の再現について聞いたところ、「カラー写真を生成してみたい」が31.8%、「音声で会話してみたい」が10.6%、「チャットしてみたい」6.7%だった。「該当なし」は55.5%だった。さらに、近年に死別経験がある人たちの方が、そうした生成に有意に肯定的だったのである。
もちろん、同じ設問で比較した訳ではないが、生成AIの普及やデジタル遺品が一般化してきたといった背景から、故人のAI再現に対する抵抗感が徐々に和らいでいる可能性がうかがえる。