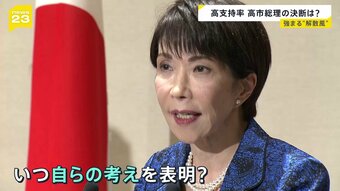■「刑務所に入ってほしくありません」「今でも、大好きです」
弁護人「娘さんが助かったと聞いたときは、どう思いましたか?」
母親「よかったと、生きていてくれてありがとうと思いました」
弁護人「事件当時のことを振り返ってどう思いますか?」
母親「異常だったと思います。周りが全く見えていませんでした」
弁護人「今回の事件を起こしてしまった自分のことをいま、どう考えていますか?」
母親「私は人に頼りきりの生活をしていました。今後は強くなって、子どもに尽くしていきたいと思います」
罪を認め、深く反省している、子どもに対して償いたいと話す母親。
その子どもたち自身の心情も、裁判のなかで読み上げられました。
長女の検察調書から
『母は明るい性格ですが、人に頼りきりで、何不自由ない生活を送っていました。父の死で、1人で全てやらなければいけない状況に追い込まれました。冷静に対処する能力がなかったのだと思います。刑務所には入ってほしくありません』
長男の弁護側提出書面から
『母は私たちに愛情を注いでくれた。いつも優しく気遣ってくれて、今でも大好きです。母には早く戻ってきて欲しいです』
■「関係は戻らない」厳しい言葉のはてに、裁判長は-
母親が罪を認めているため、今回の裁判の焦点は「量刑」-どの程度の罰が必要か、という判断でした。母親の弁護側は、有罪でも一定の期間は刑を猶予される「執行猶予」付きの判決を求め、母親が真摯に反省し、更正に向けた努力を続けていること、子ども達も刑罰を望んでいないことを訴え続けます。
判決を下すのは、3人の裁判官と、6人の裁判員たち。その中心となる神田大介裁判長が、この日の最後に、母親に問いかけました。
裁判長「あなたは子どもに手紙を出したと言いましたね。手紙は届いたの?」
母親「手紙には私はこんな気持ちだったということを書きました。事件のことには触れずに、私がこういう気持ちだったということと、ごめんなさいと、お母さんしっかり頑張るよと」
突然、裁判長の表情と語り口が厳しさを帯びました。
裁判長「こんな気持ちだったというのは、言い訳じゃないですか」
母親「・・・そうですね」
裁判長「あなたは決して許されない、最悪の選択をしたんです。それは分かりますよね?」
母親「・・・はい」
裁判長「あなたは事件のとき苦しかったと思うよ。でもこれから先、3人の暮らしに戻っても、子どもたちとわだかまりのない関係になることは、ないと思う。これからのあなたは、事件の時より、もっと大変だと思う。事件の時よりも、もっと絶望することもあると思う。それにあなたは、本当に耐えていけるの?」
母親「・・・耐えられるようにしっかり頑張るしかないです。・・・私がしっかりして、もう心配をかけないようにしないと・・・」
裁判長「それがあなたの唯一できる責任の取り方なんですよ。大変なことだよ?分かってる?」
翌日。2日目の裁判で、検察官が母親に対して求刑したのは「懲役5年」。
「確実に心臓を刺せるよう細身の刺身包丁を凶器に選ぶなど、犯行が強い殺意に基づいているうえ、短絡的、身勝手な考えで子どもを道連れにしようとした」と指摘したうえで、「夫の急死という同情に値する事情はあるものの、責任は重大だ」と、母親は実刑をうけるべきだとしたのです。
子どもたちに瀕死の重傷を負わせるという母親の罪自体は、許されるものではない。
一方で、母親も、子どもたちも、再び元の家族に戻ることを望んでいる。
罪に対する刑罰の必要性と、家族の更正の可能性。裁判所はどちらを重く考えるのか。2021年11月9日、判決が言い渡されました。