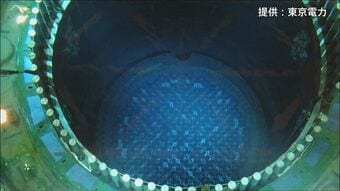学校で設置が進む「オールジェンダートイレ」が生まれた背景

Q.学校で性別にかかわらず利用できる「オールジェンダートイレ」の設置が進んでいます。反対意見はなかったのでしょうか?
黄捷委員
最初はやはり反対の声がありました。「資源の無駄遣いだ」「女性の安全が守られないのでは」といった意見もありました。「安全な空間ではない」と不安を感じる人もいました。ですから私たちがこのトイレの導入を提案した際には「これはより平等な空間であり、すべての性別の人が安心して使えるプライベートな空間です」と強調する必要がありました。
Q.どうやって不安に思う人を説得したんですか?
黄捷委員
台湾では2000年に「葉永鋕(ようえいし)事件」という出来事がありました。彼はとても「フェミニンな」男の子で、その繊細な性格のために学校でいじめを受け、最終的に亡くなってしまいました。この事件をきっかけに台湾では「性別平等教育法」が施行され、学校におけるジェンダー平等の取り組みが強化されました。
その結果、「もしすべての空間が男女という2つだけの区分だったら、さまざまな性的指向や多様なジェンダーを持つ学生に対応できないのではないか」という議論が始まり、そこで初めて「オールジェンダートイレ」という概念が議論されるようになりました。
では、どうやってより多くの人を説得するのか?私はこう考えればいいと思います。私たちはカフェなど公共の場所でトイレを使うとき、男女共用のトイレを普通に使っていますよね。なのになぜ学校では男女別のトイレしか存在できないと考えるのでしょうか?
Q.今、取り組んでいることはありますか?
黄捷委員
2年ほど前に新たに「ストーカー・嫌がらせ防止法」も制定しました。これは、性的暴行やセクハラとまでは言えないけれど、性別に関連して継続的に嫌がらせや圧力をかけるような行為に対応するための法律です。私たちは法整備を常に進化させています。
最近私たちが取り組んでいるのは「盗撮」の問題です。これは非常に厄介で、多くの場合盗撮されたこと自体に気づかないんです。盗撮された映像や画像がネットの掲示板やSNSで拡散されていても、どうやって拡がっていったのか本人にはわかりません。しかし被害にあう人はとても多いのが現状です。
こうした犯罪をどうやって防ぐかが、私たちが努力している課題であり、さまざまな法律を通じて防止に努めています。この問題の厄介なところは「被害者をどうやって見つけるか」です。なぜなら被害者自身が被害にあっていることに気づいていないからです。
これまでの性被害というのは、基本的に本人が自覚して申告することで対処されてきました。たとえば、セクハラを受けたと自覚して申告したり、性的暴力の被害を訴えるケースです。
しかし盗撮の場合は本人が被害を受けていることに気づいていません。にもかかわらず、犯罪行為は発生しているのです。ですから、加害者をどうやって特定するか、そして被害者が第一線で守られる仕組みをどう整えるかが、とても重要なのです。
聞き手 JNN北京支局 立山芽以子
撮影 JNN北京支局 室谷陽太