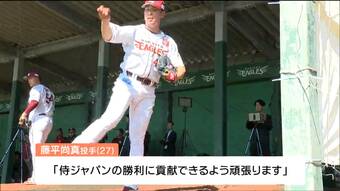簡易トイレなど衛生用品も
チラシでは、4人家族1週間分の非常食を購入する場合、総額3万円程度(カセットコンロ・ボンベは除く)になると説明しています。ただし、担当職員によりますと、このチラシは「5年以上前から使っている」ため、ここ数年の物価高は反映されていない金額となります。さらに、自宅で避難生活を送る際は、水や食料だけでなく簡易トイレなどの衛生用品も必要となります。

東日本大震災や能登半島地震では「トイレ事情」が課題となりました。内閣府の防災情報によりますと、成人の1日の平均排泄回数は1人あたり5回といわれています。これを1週間分用意する場合、1人35回分が必要です。4人家族だと35回分×4人で140回分が必要となる計算です。簡易トイレはホームセンターやインターネット販売などで購入することができます。ほかにも、トイレットペーパーやマスク、生理用品など、家庭によっては紙おむつやおしりふきなど、必要な備蓄品は多岐に渡ります。

こうして、基本的な備蓄品を書き並べていくと、一から全て用意する場合、とにかく手間とお金がかかることがわかります。その一方で、個人の備蓄品に対する公的な補助金はほとんどないのが現状です。

例えば、山形県遊佐町では、個人が用意する防災備蓄品について独自に補助制度を設けています。2万円以上6万円以下の費用のうち2分1を補助する制度で上限額は3万です。町長がマニフェストに実現を掲げていたことに加え、去年7月の豪雨災害を踏まえ導入を決めたということです。これは町独自の取り組みのため、全国的には、自宅の備蓄品については「自費」が基本となります。