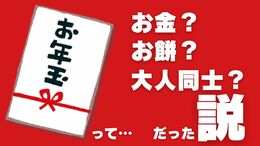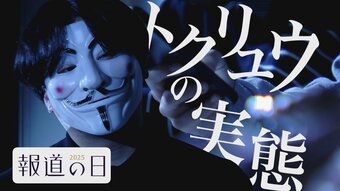失望に終わったオスロ合意 二国家共存の行き詰まり
1993年のオスロ合意は和平への期待を高めました。オスロ合意にもとづき、パレスチナでは5年間の予定で「暫定自治政府」が樹立。当初、この5年間の間にパレスチナ問題の解決を目指すことになっていました。
しかし、和平は実現しませんでした。鈴木特任准教授は「いつの間にかパレスチナは『暫定自治』と呼ばれなくなり、今では『自治区』または『パレスチナ自治政府』と呼ばれます。5年間続くだけだったものが、30年以上にわたって続いている」と指摘。「和平への期待が膨らんだ分、実現されなかったことの失望も大きかった」と振り返ります。
二国家共存の理念も行き詰まっています。オスロ合意では、イスラエルに並んでパレスチナ人が国家を作り、戦争ではなく話し合いで問題を解決していく方向が目指されました。
「いま研究者の間では『一国家状態』という言い方が使われます。イスラエルという国家が全てを管理している。パレスチナ自治政府の主権というものも、イスラエルの意向によってほぼ制限されるという状態になってしまっている。今回のガザの戦闘を見て、『二国家共存は無理かもしれない』という考えが広まっている」と鈴木特任准教授は説明します。
現地の窮状—食料、水や医薬品が不足
ガザの飢餓は極めて深刻です。
国連人道問題調整事務所(OCHA)が5月28日に発表したまとめでは、 ガザに住む約210万人の全員が、何らかの食料不足に直面しています。このうち47万人は、食料の状況を示す国際的な指標で、5段階で最悪の「壊滅的飢餓」に直面し、さらに100万人が2番目に悪い「人道的危機」にあるとされています。
「パレスチナ子どものキャンペーン」の手島正之さんは「食事を一日一食しか取れない状態。その一食はお米やパスタなど、簡単なものです野菜や肉は滅多に手に入らない状態」と現状を説明します。
空爆で家を失い、避難する人たちは、過酷な移動を強いられています。手島さんは「ほとんど徒歩で何十キロも歩かなければいけないという状況が続いています」と語ります。また「多くの人たちが、ロバが引く荷台に乗って移動することも今では一般的になっている」ということです。
現地で給水支援を行う手島さんは「『支援が来なければ海水を飲もうとしていた』と言う人もいますし、実際に飲んだことがあるという話もどんどん聞こえてくる」と、現地の深刻な状況を伝えています。