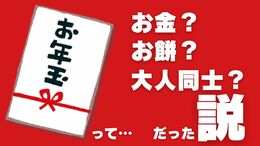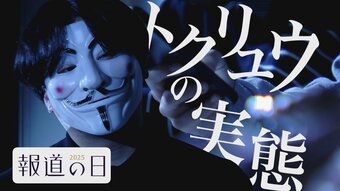交渉の行方は 「ハマスの反撃力、著しく低下」
イスラム組織ハマスは交渉にどう臨むのか。鈴木特任准教授によれば、ハマスはイスラエルの人質がガザ地区に60人近くいると主張しています。ハマスは人質の解放と引き換えにガザ地区での停戦、そしてイスラエル軍の撤退を求めている状態です。
一方で、「戦闘という観点でいえば、特にこの3月以降のこの2ヶ月ほど、ハマスから有効な反撃はほとんどなかった」と鈴木さんは分析します。戦闘再開後、イスラエル軍兵士の死者数が、戦闘再開以降わずか7名であることから、「戦闘という形になっていない」と指摘します。
「ナクバ」から続くパレスチナの悲劇
パレスチナ問題の背景では1948年のイスラエル建国時に起きた「ナクバ」と呼ばれる出来事が特に重要です。
1948年、イスラエルが建国されました。これと前後して、パレスチナに住んでいた人々の多くが、戦闘と追放によって家を追われ、難民となります。
鈴木特任准教授によると、パレスチナの当時の人口140万人のうち、半数に上る70万人が難民化しました。パレスチナの人々はこの出来事を「ナクバ」(アラビア語で「大惨事」)と呼んでいます。
「1948年のナクバはパレスチナに暮らしていた人々が故郷を失い、自らの土地や家族とのつながりを失ってしまう体験でした」と鈴木特任准教授。「自分たちのことを『パレスチナ人』と認識する原体験になって、『あの時失われた故郷を取り戻したい。取り戻せないのであれば、それに見合った補償をしてほしい』というパレスチナの人々の願いの根源を作り出しました」
1967年には第三次中東戦争で、イスラエルが東エルサレムを含むヨルダン川西岸、ガザ地区などを占領。国際社会はこれらの地域を「占領地」とし、イスラエルに撤退を求めてきました。
1993年には「オスロ合意」と呼ばれる和平の枠組みが作られました。将来的な二国家共存が期待されましたが、和平は進みませんでした。
2006年には、パレスチナ立法評議会選挙でイスラム組織ハマスが勝利。翌年、イスラエルとエジプトはガザを封鎖し、人や物資の出入りを厳しく制限します。現在まで続く、ガザの「封鎖状態」の始まりです。