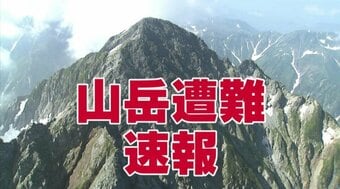「いつもより多めに買う」で価格が大きく変動…コメの特殊性
コメは他の商品とは異なる特性を持っています。小川さんによれば、「コメは需要曲線の傾きが普通の商品とは違い、少しの需給の変化で価格が一気に上がったり下がったりする特徴を持っています」。
具体的には、「玄米20万トンほどの変化で価格が大きく変動します」と小川さん。これは国民1人1日あたり小さじ1杯分、年間で1世帯あたり3.3kgに相当します。つまり、「普段よりも5kgの米袋を1袋多く買っただけで、かなり価格が動いてくる」のがコメの特徴なのです。
こうしたコメの価格はどのように決まるのでしょうか。小川さんによれば、基本的には需要と供給のバランスで決まりますが、「日本では確立したコメの市場がない」ことが特徴的です。
「一言でコメと言っても、産地や銘柄、品種によって評価や味が違います。そのため『コメはこの値段』という統一された一つの価格に決まるわけではない」と小川さん。また、日本でコメは基本的に年に1回しか収穫されないため、例年でいえば、「主に収穫時に今後1年間を見通して契約したり基本的な価格が決まっていく」という特徴があります。
備蓄米放出のタイミングは適正だったのか?
備蓄米の放出をめぐっては、そのタイミングや政策としての評価が問われています。小川さんは、「去年の夏に備蓄米放出を要請されて断ったのは良かった」と評価する一方、今年1月の対応は「遅かった」と指摘します。
「昨年10月30日に農林水産省がコメの品質状況分析結果を発表した時点で、備蓄米放出の検討を匂わせるだけでも、年末から年明けにかけての価格高騰は抑えられたのではないか」と小川さんは考えています。
さらに、備蓄米の本来の目的について、「基本的には災害や大凶作のために備えているもの」と強調します。「今年南海トラフの大きな地震や大凶作が起きた時に備蓄米が政府の手元にないということになる」とし、政府は「大きなリスクを背負いながら決断した」と分析しています。
また、政策の一貫性の問題も指摘します。当初は「物流対策」として導入され、価格には介入しないと強調していたにもかかわらず、途中から「価格を落ち着かせるため」という目的にシフトしたことで、「政策がぶれると失敗しやすい」と懸念を示しています。