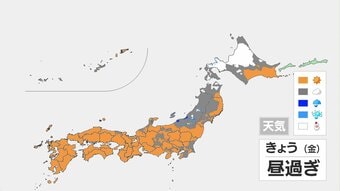コメの価格が依然として高値が続き、消費者や生産者の間で不安や戸惑いの声が広がっています。なぜ今、コメの価格がこれほどまでに高騰しているのでしょうか。他の食品とは異なる市場の特殊性、備蓄米放出のタイミングの評価など、宇都宮大学助教で農業経済学者の小川真如さんに、日本のコメをめぐる現状と課題について聞きました。
18週ぶりの価格下落 備蓄米放出の効果
4月28日から5月4日までに販売された、スーパーでのコメの平均価格が18週ぶりに下落に転じました。江藤農林水産大臣(当時)は「消費者の方々が大いに評価する水準にはない」と述べましたが、この価格下落はなぜ起きたのでしょうか。
「備蓄米の効果が出てきて、値段が下がってきたと見ています」と小川さん。購入量の約3割は備蓄米と見られており、その効果が価格に反映されたとのことです。
ただし、備蓄米が放出されてから価格に反映されるまでにはタイムラグがあります。これは「コメは重さもありますし、かさばりますし、精米という工程も加える必要があります」と小川さん。
また、備蓄米はブレンド米として出荷されることが多く、パッケージデザインや袋詰め作業にも時間がかかります。年度末や連休を挟んだこともあり、トラック輸送や人員確保の課題もあったとみられます。
需要増でも「コメだけ価格が上がらなかった」価格高騰の理由
昨年夏以降から続いたコメ価格の高騰。その発端はどこにあったのでしょうか。
「価格高騰の発端は2023年、需要と供給ともに大きな変化があったことです」と小川さんは指摘します。
供給面では、2023年の猛暑がコメの品質低下をもたらしました。「コメは暑さに弱い面があり、品質が大幅に低下したり、加工用に使うコメが減ったりしました」。精米時に割れてしまうなど、精米としてコメを売るにあたって、必要な玄米の量が増えたことも影響しています。
一方で、需要は増加傾向にありました。「日本ではコメの需要量が長年下がってきた傾向があるなかで、大きく増えたという特徴がありました」。
その背景には、コメが「当時安すぎた」という事情があります。物価高騰、さらにはウクライナ危機を背景にパンや麺類の価格が上昇する中、コメだけが「異常な形で価格が上がらない、むしろ下がるような局面もあった」ため、相対的にコメへの需要が増加したのです。
さらに、コロナ禍の収束に伴う外食産業の復活や、インバウンド需要の増加も要因となりました。これに加え、南海トラフ地震臨時情報による備蓄意識の高まりが、夏場の品薄時期と重なり、コメの品薄と価格上昇に拍車をかけました。