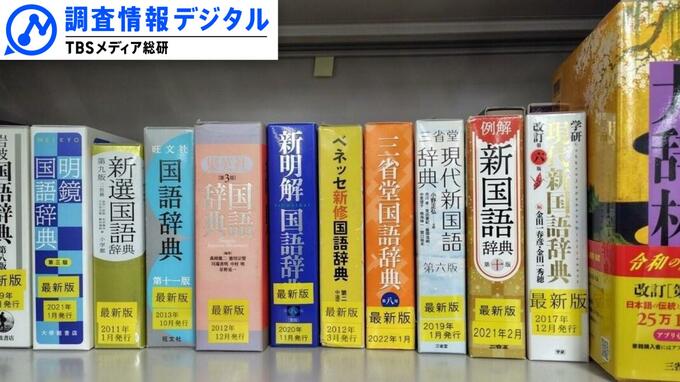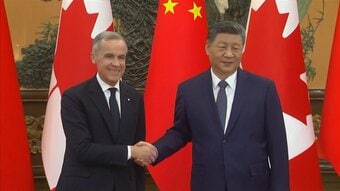「不用品」と「不要品」の使い分けは?「一品」と「逸品」では出てくるものが違う?「対処療法」は合っている?「組織の体をなしていない」、何と読む?TBSテレビの言葉の番人、内山研二が最近気になった事例を紹介する。
はじめに
私の職場は「審査部」です。番組やCMなどの表現に問題がないかを確認し、どのような表現がより良いのかを探る職場です。その「審査部」で、放送表現や放送用語を担当しています。
「言葉はいきもの」といわれ、本来とは違う意味や使い方をしている言葉は多くあります。その本来とは違う意味や使い方を、どこまで許容できるかに悩まされます。そんな職場で出会った印象深い「言葉たち」をいくつかご紹介します。
よく耳にしますが、よく考えると「?」
多くの方は、朝起きてから夜寝るまで「スマホ(スマートフォン)」が手元にない時間のほうが少ないでしょう。ネット検索、メール、SNSはもとより財布の機能まで、「スマホ」は必需品です。
そんな「スマホ」をめぐってよく耳にするのに、よく考えると「?」となる表現があります。「充電切れ」です。
周囲の多くの人が「充電切れちゃう」「充電切れになる前に充電しよう」などと口にします。この場合の「切れる」は「電力がなくなる」という意味です。正確には「電池(の電力)が切れる」「バッテリー(の電力)が切れる」ですよね、と質問を受けました。
「充電」は「電池などに外部から電気を蓄えること」で、「電池」「バッテリー」そのものではありません。厳密に意味を考えれば「充電切れ」は「電池(バッテリー)に充電している途中で、充電することをやめる(充電することができなくなる)こと」となります。それでも「充電切れちゃう」「充電切れになる前に充電しよう」は、よく耳にします。
こうした表現がどうして広く使われているのでしょうか。「充電しなくては」という思いがあるため、対象である「電池」「バッテリー」が、行為である「充電」に置き換わったのでしょうか。
「電池が切れる」「バッテリーが切れる」「電力が切れる」などが望ましい使い方ですよと質問に答えましたが、「充電切れ」の広がりを止めるのは難しいでしょう。いずれ国語辞典に用例として掲載されるかも知れません。
どちらも「いらない」ものですが
「不用」と「不要」の使い分けを知りたいという相談がありました。さらに聞くと「不用品」と「不要品」の書き分けに悩んでいました。どちらも「いらないもの」に変わりはありません。
「不用」は「用のないこと」「役に立たないこと」といった意味で、対語は「入用」です。「不用になった本」「不用な施設」などと使います。
「不要」は「必要でないこと」「いらないこと」「求めないこと」といった意味で、対語は「必要」です。「説明は不要」「不要不急」「不要な出費」などと使います。
「不用品」と「不要品」は、どちらも「手放してよいもの」ですが、「不用」には「役に立たないこと」という意味があります。「役に立たないもの」には「壊れて使えなくなった」という意味も含まれます。
すると「不用品」には「壊れた物」も含まれると解釈できます。「不要品」は「いらなくなった物」、「不用品」は「壊れて使えなくなった物も含む、用のない品」と解釈できます。その点を考慮して使い分けるとよいのでは、と答えました。
答えたあとに「不用な人(役に立たない人)」「不要な人(必要ない人)」。どちらも言われたくないなと、ふと怖くなりました。
漢字「ひと文字」がもつ意味の広さ
ときどき耳にする「ずさんな運営をして、組織の体をなしていない」といった表現の「体」の読み方について考えさせられました。
多くの方は「てい」に馴染みがあるのではないでしょうか。「組織の『てい』をなしていない」と言うほうが、すわりがよく感じます。
ところが、審査部で扱う14冊の国語辞典の掲載を調べてみると、「たいをなす」「たいをなさない」と掲載されています。「組織の『たい』をなしていない」となるのです。しかし、私を含め周囲も「てい」派が多く、「『たい』なの?」という反応です。
では「てい」はだめなのかと、国語辞典で「体(てい)」の項目を調べます。用例として「体(てい)を成している」を掲載する辞典(新明解国語辞典第八版・三省堂)がありました。こうしたことから、「たいをなす・たいをなさない」を読み方の基本にし、「ていをなす・ていをなさない」も許容できるということにしました。
ただ「たい」と「てい」の意味合い・解釈に差はないのかと、もう少し調べてみると「たい」について多くの国語辞典は「まとまった形」「形態」といった意味を掲載しています。一方、「てい」について、多くの辞典は「見た目」「姿」といった意味を掲載しています。
すると「組織の体(たい)をなしていない」は「組織が機能していない」という意味合いが強く、一方、「組織の体(てい)をなしていない」は「組織の実体がない」という意味合いが強いのではないかと解釈できます。
これは「体」という漢字「ひと文字」についての話ですが、読み方によって意味合いに差があるものは、まだまだありそうです。