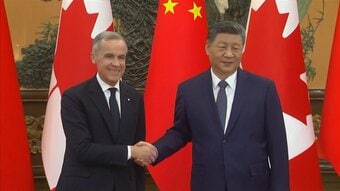「重ねる」は、どこまで許容できるのでしょうか
「甲冑(かっちゅう)」に、どんなイメージがありますか?「甲冑」は、胴を守る鎧(よろい)と、頭にかぶる兜(かぶと)の総称ですから、鎧兜姿の重厚な武将の姿を思い浮かべる方も多いでしょう。
ところが「甲冑=鎧」と間違えて「甲冑に兜のいでたち」「甲冑姿に兜をかぶり」といった表現をしてしまうことがあるようです。これでは「兜」の上に「兜」をかぶるという妙な出で立ちになってしまいます(そもそも、かぶれないでしょうね)。これも「重ね言葉」になるのかなと思いました。
その「重ね言葉(重言)」は、使い方によって強い違和感を与えます。「馬から落馬する」「電車に乗車する」などが典型的な例です。「馬」や「車」が連続して表記されますから、強い違和感を与えるため「誤り」と位置づけられます。
一方で、放送は「話し言葉」が中心です。耳にしたときに違和感があまりないものもあります。
例えば「いま現在」はどうでしょう。「いま現在、こちらでは○○○といった状況です」などと聞き覚えはありませんか?「いま」も「現在」も同じ意味なので「重ね言葉」といえます。ただ、「いま現在」を口にする場合は、「いま」または「現在」を強調したいときに口にすることが多いのではないでしょうか。
このように「重ね言葉」は、強調したいときに口に出ることがあるので、「話し言葉」として許容できるのではとも思っています。
また、「花が開花する」も「重ね言葉」なので、「花が咲く」などに言い換えれば違和感はなくなります。ところが「桜の花が開花する」というように「桜」という「新しい情報が加わると適切な表現になる」と解説する国語辞典(明鏡国語辞典第三版・大修館書店)があります。「桜の花が咲く」に言い換えられますが、この解釈は参考になります。
「重ね言葉」は正誤を判断するのが、難しいです。
「あいまいな記憶」に漂う言葉
その言葉をおぼえたのはいつ、どこで、どうして、などと記憶をたぐるのは難しいです。その言葉は「そう言わないのだ」と知ったときは、さらに記憶をたぐる難しさを感じます。まさにそんな「あいまいな記憶」の中に漂っていた言葉がありました。
「うろ覚え」です。「うろ覚え」はご存じのように「ぼんやりと覚えていること」「不完全な記憶」といった意味です。これを「うる覚え」と記憶していたのです。いつ、どこで、どうして記憶したのか、かなり前のことのようです。
国語辞典を調べると「うる覚えは誤り」と掲載するものがあり、「あれれ」となりました。60歳を過ぎた最近まで長いこと「うる覚え」とつき合っていたのですから、これまで日常会話のなかで「うる覚え」を口にした回数はそれなりにあったはずです。
けれども「間違っているよ」と言われた記憶はないようです。一方、三省堂国語辞典第八版には「なまって、うるおぼえ」と掲載されています。もしかすると「なまった」環境の中で覚えてしまったのかもしれません。「記憶はあいまいなものだなあ」と恥じながらも、「あいまいのままでもよかったのになあ」という声が心のどこかで響いたのは確かです。
とはいえ「『うろ覚え』としっかり記憶しよう」と、自らに言い聞かせました。
どちらも美味しいのです
「当店自慢の『いっぴん』です」と出てきた料理があるとします。「いっぴん」には「一品」と「逸品」があります。では、「当店自慢の一品です」と「当店自慢の逸品です」とでは、出てきた料理は違うのでしょうか。
「一品」「逸品」ともに「最もよい品」と共通する意味があります。
「一品」は「いっぴん」と読みますが「ひとしな」とも読むように、「一つの品(物)」の意味があります。一方、「逸品」には「一つの品」という意味は含まれていません。このことから「当店自慢の一品です」は、「一つの品」「一品料理」ということになります。
「当店自慢の逸品です」は、「一つの品」に限りませんので「品数の多い」料理かもしれません。どちらも美味しい料理に違いありませんが、「一品」と「逸品」…どんな料理が頭の中に浮かびますか?
放送では「一品」も「逸品」も「いっぴん」と読むので、「おすすめの一品」という場合は、「ひとしな」と読むことで「逸品」との混同を避けられますよとしています。また、「天下一品(=比べるものがないほど、すぐれているもの)」は四字熟語なので「天下逸品」は使いません。「逸品」を使いたいときは「天下の逸品」となります。