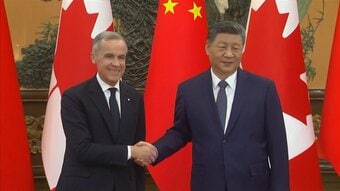「発音」も大切です
発音が似ていることから、間違えてしまう表現があります。特に放送の場合は、発音と表記が対になることが多いので、発音がうろ覚えですと、表記も間違える可能性が高まります。
そんな言葉に「対処療法」があります。医学用語の「対症療法」を誤ったもので、「たいしょ」「たいしょう」と「う」の有無だけですし、「対処」は馴染みのある言葉ですから、つい「対処療法」としてしまいます。
「対症療法」は、根本的な治療ではなく、高熱に対して解熱剤を使うといった「症状に対する治療」のことです。本来は医学用語ですが、転じて「その場しのぎの処理」といった意味でも使われるケースは多くあります。「根本的な解決とはいえない判断」という意味で「その判断は対症療法に過ぎない」といった使い方をしますね。
「対処」を使うのであれば「その判断は一時的な対処に過ぎない」「その判断は暫定的な対処に過ぎない」といった表記になるでしょう。発音が似ていますし、似たような使い方もできますから、うろ覚えですと間違えてしまうのです。ただし、「症状に対処するための療法」を略した「対処療法」が許容される日がくるのかもしれません。
おわりに
この仕事に関わって7年がたちました。「言葉の使い方」「表現の仕方」を調べて記録するうちに、正誤の判断ができないものが増えてきました。
最初のころは正誤の判断が容易だった「言葉」が多かったのですが、記録の数が増えるにつれ、何となく後回しにしていた「言葉」たちが列に並んでいて、気づくと目の前にいたのでした。その「言葉」たちの「表情」は複雑で、どうしたものかと腕組みします。
日本語は良くも悪くも「あいまい」なのですから、「あいまいは、あいまいのままでよいのかも」と、思うこともあります。ただ、相談が寄せられれば、返す必要があります。腕組みを解いて、額に手をやり、頭を抱えて、その「言葉」と「にらめっこ」…そんな日々です。
<執筆者略歴>
内山 研二(うちやま・けんじ)
1963年生。1987年東京放送入社。ラジオ記者、ラジオ制作、ラジオニュースデスク等を経て、2018年より審査部。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。