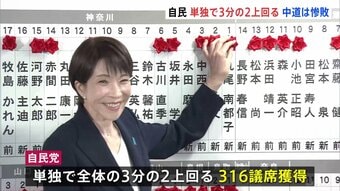■国後島に向かう船の問題も
もしも仮に国後島での遺体返還が実現していたとしても、海上保安庁が派遣する船については、微妙な問題があった。
日ロの調整がまとまり、最終的に9月にサハリンまで遺体を引き取りに行った海保の巡視船「つがる」(PLH型、ヘリコプター搭載、3100トン)は、海保が保有する中で、国際航行が可能な最大級の船だ。国際条約(船舶バラスト水規制管理条約)で、国際航行するためには「グレイウォーター」と呼ばれる生活排水を浄化するための特殊な設備(タンク)が備わっていることが求められている。
しかし、日本政府は「国後島は日本の領土」という立場をとっていて、北海道から目と鼻の先にある国後島に航行する場合、「つがる」のような国際航行可能な大型船で行くことは考えられず、また国後島の港には「つがる」のような大型船が接岸できる設備はないため、小型の巡視船で向かっただろう。
2006年に銃撃して死亡させた乗組員の遺体返還の時とは違い、今回は海難事故の犠牲者の遺体返還である。ロシアにとって、日本側が「国後島は国内だ」との前提で小型巡視船で来ることは、看過し難い状況だったのではないだろうか。
結局、日本政府からは、上記の「中間線案」「国後島案」の他にも、「ロシア側が日本に届ける案」なども含め、様々な提案を外交ルートで投げたというが、いずれも合意には至らなかった。
■「この機を逃してはならない」台風迫る中の“見切り出航”
こうした中、第4の案も検討されていた。
6月28日、サハリンで乗客男性の遺体が発見されたとロシアから伝えられた。
当初は、国後で発見された2人の遺体とは別に返還する方向で調整が始まったが、その後、国後で発見された2遺体をサハリンまで送り、海保の巡視船で3人の遺体をサハリンでまとめて引き取る案が浮上したのだ。サハリンは国後島と違い明確にロシア領であり、大型の巡視船で向かうことに何の問題もない。

8月23日、ロシア外務省から「3遺体をサハリンで海上保安庁の巡視船に引き渡す」との回答が得られ、日ロ両政府はついに合意した。
すぐに、海上保安庁の巡視船をサハリン南部のコルサコフ港に入れるための「口上書」(相手国に意向を伝える外交文書)をロシア側に提出する手続きが始まった。サハリンのロシア外務省関係者からも、「遺体を返還できるので来港して大丈夫」との言質が得られていた。
9月上旬には、遺体返還を9月9日に行うという具体的なスケジュールがロシア側からもたらされた。国後島から遺体をフェリーで移送する手配や、サハリンでの遺体の保管、巡視船の入港手続きなど、日ロ関係者たちが9日をターゲットとして各所で動き始めた。
さらに、海上保安庁には、船会社から「国後島で発見された2人の遺体がフェリーでサハリンに移送された」との情報も入っていた。日本政府関係者たちは、遺体はきっと返還されると確信を強めた。
しかし、最後の懸案は、北ではなく南からやってきた。

9月4日の台風11号の進路予想
折しも、東シナ海から日本海を通って大型の台風11号が北上してきていた。台風に足止めを食って巡視船がサハリンに向かえなくなれば、9日を軸に進められた諸々の手続きがすべて無駄になり、スケジュールをゼロから組み直すことになる。
「この機を逃してはならない」
この時点で、口上書に対するロシア政府からの正式な文書回答がまだ来ていなかった。口上書の回答が来なければコルサコフに入港することはできない。
政府関係者たちは「航海中に回答はきっと来る」と信じ、9月8日午後1時すぎ、海上保安庁の大型巡視船「つがる」が北海道・小樽から出港した。「見切り発車」ならぬ、「見切り出航」だった。