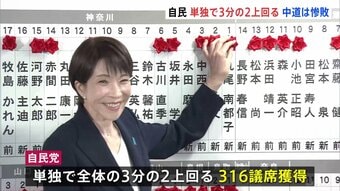■当初提案した“中間線での引き取り案”とは
返還の調整に時間がかかったのは、やはりロシア特有と言ってよい幾つかの事情があった。
5月、2人の遺体が見つかったのは、ロシアが実効支配する北方領土・国後島だった。海上保安庁は当初、北海道と北方領土との中間線付近の洋上で遺体の引き渡しをしてはどうかと外務省に提案し、ロシア側に伝えてもらったという。
中間線をめぐっては、2007年12月にロシア国境警備局の警備艇が日本の漁船4隻を拿捕した件で、翌年2月、北海道庁所属の漁業取締船が中間線付近の根室沖で乗組員4人の引き渡しを受けたことがあったが、中間線での遺体の引き渡しは前例がなかった。
当初、ロシア側からは肯定的な反応が返ってきており、この案はまとまるかに見えた。しかし、中間線での引き渡しの場合、ロシア側は国境警備局所属の船が向かうのだが、これについてロシア国内での調整ができず、実現しなかった。
■前例のある“国後島での引き取り案” しかしウクライナ侵攻の影響が
次に、国後島に海上保安庁の船で遺体を引き取りに行く提案がされた。
国後島での遺体の引き渡しについては、2006年8月16日に漁船「第31吉進丸」がロシア国境警備局の警備艇に銃撃・拿捕され、乗組員1人が死亡した事件で、発生から3日後の8月19日、遺体を国後島に引き取りに行った例がある。
この時、海上保安庁の巡視船「さろま」(PS型180トン)が国後島に赴いたが、海保職員の他に外務大臣政務官も同乗しており、国後島に上陸し、ロシア側に拘束されていた乗組員3人と面会した。
当時、ロシア側は旧島民に対し、北方領土にある墓参りのための「ビザなし渡航」を認めており、国後島に遺体を引き取りに行った日本政府関係者たちは、この手続きが簡略化された「ビザなし渡航」で国後入りしたのだった。
こうした前例があったため、今回の国後島での遺体返還について、日本側はかつてと同様「ビザなし」での入島を申し入れたという。しかし折悪く、観光船事故の約1か月前の3月21日、ロシア政府は、ウクライナ侵攻後に日本が欧米諸国と共に行った対ロ制裁を理由に日本との平和条約締結交渉を中断し、あわせて北方領土の元島民らによるいわゆる「ビザなし交流」を停止する意向を一方的に表明した。
そのため、国後島での引き渡しについて、ロシア側の返答は「国後島に来るのならビザ取得など正式手続きをする必要がある」というものだった。
日本政府としては、「国後島は自国の領土」という認識のため、ロシアのビザを取得して国後島に上陸することはできず、この案は折り合いがつかず頓挫してしまった。
政府関係者は、このことが、遺体返還を長期化させる大きな要因となったとみている。