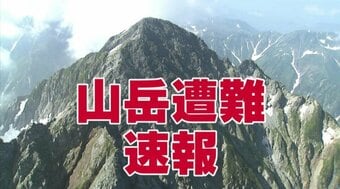ちゃんとした料理を ちゃんとした値段で 提供する責任
――次に話していただくテーマは何番でしょうか。

村田吉弘氏:
12番の「つくる責任 つかう責任」です。
――この実現に向けた提言をお願いします。

村田吉弘氏:
ちゃんとしたものをちゃんと出す。
――ちゃんととは?
村田吉弘氏:
ちゃんとしたものをちゃんとした値段でちゃんと出す。ちゃんとした生産者からちゃんとしたルートで食材を仕入れ、ちゃんとした料理を作り、ちゃんとした適切な価格で提供する。
ブランドがあるから「高い値段」というのは納得できない。高い方がおいしいとかは悪い風潮。そうすると高い方に行く。7万円の寿司屋が流行る。ありえない。半分ぐらい家賃だ。
食べることは積み重ねです。小さい頃からちゃんとしたものを食べてきた人は、味がわかります。急に儲けて高級店に行く人たちは、値段で味を判断します。
予約が取れないことを自慢する店もおかしいです。1年先の予約を取るなんて、生きているかもわからないのに無意味です。同じ人がぐるぐる回している。公共性ゼロだ。自分は色んな人に料理を食べてもらいたい。
――料理屋の「公共性」とは?

村田吉弘氏:
電話帳に番号を載せて、暖簾下げて商売をするということは、自分のためではない。料理屋は公共の施設です。誰のための施設かと。自分のためにつくっているという人が多い。「気に入らなかったら食うな」みたいなかんじ。
しかし、料理とは「理(ことわり)を料(はか)り定める」と書いて料理。5歳の子どもから95歳のおばあちゃんまで、皆に合わせた料理を提供するのが料理です。同じものを出すだけでは料理とは言えません。
例えば、普段はやっていないが、茶碗蒸しを冷ましてから出したり、工夫することが料理です。八坂神社の近くで始まった京都の料理屋は、おばあちゃんにお宮参りに抱かれてやってくるところから始まる。七五三、成人式、結納、喜寿、米寿など、一般の人々が来る場ということが大前提。料理は味だけでなく、人の琴線に触れるものです。
入退院を繰り返していた80代の老人が、梅の花が咲いていて、お香が漂う座敷の中で、蕗のとうの味噌揚げを食べて「生きててよかった」と言ったことがあります。これは値千金だと思うのは、メンタル的なところにひっかかっているから。そういうものをつくらないといけない。
おばあちゃんの味噌汁が美味しいのは、味だけでなく家の匂いや雰囲気が含まれているからです。食は単純でありながら複雑で、記憶に残りやすい。まずかったものとか結構覚えている。新婚旅行の美味しいパスタも覚えている。観光地の記憶は忘れても、レストランで何を食べておいしかったという記憶は残りやすい。
――チェーン店の牛丼はたべますか?
村田吉弘氏:
吉野家の顧問をやっていました。あんなに一日に消費される日本料理はない。顧問になる前の話ですが、吉野家の社長が店に来たとき、「牛丼の玉ねぎのシャリシャリ感が時間帯で変わる」と話しました。「一つの商品であれだけ安定していないのもすごい」と。そしたら1週間後ぐらいに、「顧問になって欲しい」といわれました。
「生だれ(原料を非加熱でブレンドしたたれ)で流通させると美味しい」といったら「生だれではまわしてない」といわれた。でもそれはおかしいと。生だれの方がおいしいとわかっているのなら、コストが掛かろうと、まわす工夫をするのが料理人だと。生だれにしたら、売り上げが2割増えた。安いから適当でいいという考えは間違いです。
マクドナルドのハンバーガーを否定する料理人もいますが、世界で愛されるものを評価できないのはおかしい。「吉野家の牛丼が一番おいしい」としかいえない立場ではありますが。