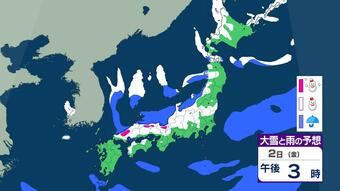ジェネリック時代のマーケティングとは?
野村:
今後はブランド名だけでなく、「どこで差別化するのか」という点と、「価格の正当性をどうするか」という点が重要になりますね。一方で、高く売れることは悪いことではなく、それが経済成長を生み出した側面もあります。コスパ重視になり均衡する先がどうなるのかと個人的に気になります。
comugi:
そうですね。二極化することはあると思います。
高品質で低価格のジェネリックが登場していますが、例えば日本のアニメキャラクターをパッケージにつけるなど、「キャラクター物」として日用品を作るといった動きがあります。それは付加価値を作る方向性として今も昔もありましたが、今は顕著になっていると感じます。
ちょうど今日セブン-イレブンに寄った際、チョコレートブランドの「ダース」のパンが登場していました。セブン-イレブンもパンに既存のブランドを入れるとは驚きましたが、このようにブランドを横展開する方法は徐々に増えている印象があります。今までブランド=商品だったものが、そのブランド価値をちょっと横にずらして違う商品に転用していきましょうという動きが見られます。
一方で、ドン・キホーテでルイ・ヴィトンのバッグが売られていることには違和感がありますよね。もう少し購買の体験価値が意識された高級品に再構築されることを期待します。
例えば、ビール会社が自分のビール会社の工場を追体験できる、イマーシブ型の施設を作り、飲み比べをして味を確かめることができるという事例があります。ペアリングで美味しい食べ物とセットでおすすめすることは、まさに体験です。
体験したことがそのままプロダクトの価値に繋がる動きが多く見られるようになっています。従来のマーケティングは4Pなどのフレームワークに基づいていました。しかし、「ジェネリック〇〇」の躍進によりブランドの体験価値が求められるようになった今では、その枠組みで捉えきれない情報環境になっていると思います。
<聞き手・野村高文>
音声プロデューサー・編集者。PHP研究所、ボストン・コンサルティング・グループ、NewsPicksを経て独立し、現在はPodcast Studio Chronicle代表。毎週月曜日の朝6時に配信しているTBS Podcast「東京ビジネスハブ」のパーソナリティを務める。