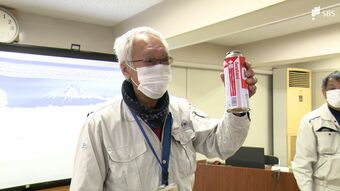「街なかとスタジアムを結ぶハブ…これまでのビジネスと違う」

2月19日水曜日、アジアチャンピオンズリーグ2のノックアウトラウンドのゲームが行われた。キックオフ時間が迫る中、スタジアムへと向かう仕事帰りの人の姿が多くあった。
エディオンスタジアム時代の平日夜開催は、Jリーグのリーグ戦でも観客動員に苦戦、国際大会ではなおさら厳しかったというが、この夜の観客数は9,471人と、これまでの平日開催の倍近いの数を記録した。
サポーターからも「(ピースウイングが)行きやすいところにあり、本当に良かった」「(以前のスタジアムでは)帰りのバスが混んでいたが(ピースウイングは)そこが解消されている」と好評だ。

新スタジアム周辺は、路面電車、アストラムライン、バスに、JR線と、多くの交通手段があり、いずれも徒歩10分から20分圏内。ネックだったアクセス面は格段に改善された。
課題もある。ピースウイングのある中央公園は、都市公園法に基づき整備された公園のため、長崎のように、というわけにはいかない。そこで、問われるのがどうやって収益性を高めていくかだ。そこで、広島市は、スタジアムを「多機能施設」として、試合が行われない日も稼働すること前提に、スタジアムと芝生広場を一体にした整備を実施。「(ピースウイングが)収益を365日あげられるような工夫」(藤川課長)を施した。
例えば、スタジアム内には、大小さまざまな部屋を設置。試合後に使われる会見場は企業の発表会に使われたほか、スタジアム自慢の大型ビジョンを使って医療系の学会が行われたり、一周できるコンコースを使っての駅伝大会も開かれたりした。さらに、芝生広場の周辺には飲食店やサウナなどが入る商業施設を建設。指定管理者はサンフレッチェが担う。

森重部長は「街なかにスタジアムがあるということは、サンフレッチェが『まちづくりに参加する』ということ。皆さんもこれを期待されている。街なかとスタジアムを結ぶハブの役割として、様々なコンテンツを提供できるかを考え、行動に移していくというはこれまでのサッカービジネスと違う」と話す。
そのうえで「有意義な時間の過ごし方をサンフレッチェが提案することで、地域の中になくてはならないスタジアムという形になれば」を未来を見据える。
では、静岡はどうか。