SDGs達成期限の2030年に向けた新たな価値観、生き方を語る今回の賢者はグラフィックデザイナーの佐藤卓氏。「キシリトールガム」や「おいしい牛乳」など暮らしの中の身近な商品を数多くデザインしている。その始まりは、28歳のときに手がけたウイスキーのボトルとパッケージだ。当時としては斬新な再利用を考えたデザインで、40年以上も前から環境問題に向き合っている。2021年には紫綬褒章を受章。14年にわたり子どもに向けたデザインの教育番組の総合指導を務めている佐藤卓氏に、2030年に向けた新たな視点、生き方のヒントを聞く。
見た目だけがデザインじゃない。佐藤青年とLPレコード
――賢者の方には「わたしのStyle2030」と題して、話していただくテーマをSDGs17の項目の中から選んでいただいます。佐藤さん、まずは何番でしょうか?
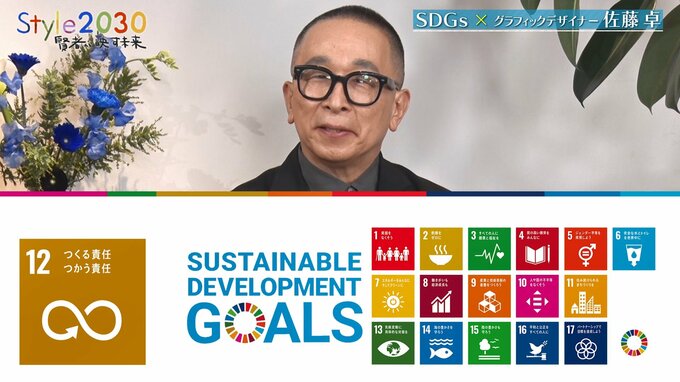
佐藤卓氏:
12番の「つくる責任 つかう責任」っていうのを選ばせていただきました。
――この実現に向けた提言をお願いします。
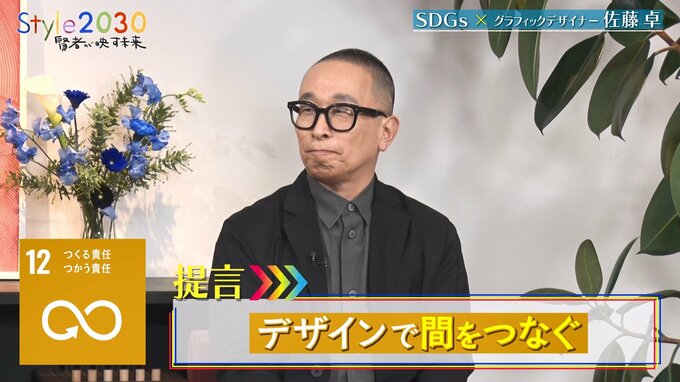
佐藤卓氏:
「デザインで間をつなぐ」っていうふうにさせていただきました。
――まず、佐藤さんにとってデザインとは?を定義していただけますでしょうか。
佐藤卓氏:
はい。長年いろんなデザインの仕事に関わってきて、つくづく自分がやってることは、間を適切に繋ぐっていうことを心がけてきたんだなって思うようになったんです。
とかく形とか色とかがデザインだと一般的に思われがち。例えばかっこいいものとか、洗練されたものとか、かわいいものとか、おしゃれなものとか、そういうものにはデザインが施されていて、そうじゃないものはあまりそういうふうに見えないっていうか。
でも、いろんなデザインが実は社会には潜んでいるわけなんです。例えば我々が座っている椅子は、座ることっていう私達が普段やっていることと人を間で繋いでるわけです。
椅子がデザインで語られるんですけど、それが人に提供しているものっていうのは、座り心地なんです。デザインっていうのは目的ではなくて、人とか環境とかいろんなものの間を繋いでいるんだなって思うようになりました。
――目に見える部分がデザインというふうに考えがちですが、捉え方が広いんですね。
佐藤卓氏:
デザインと関わりのない物事は何一つないって言い切れるようになりました。誰もが普段、例えば家の中の物をどこに置くか、ある意味ではインテリアの空間のデザインをしてるわけです。我々の身なりとか髪型、お化粧。自分の好みを伝えて、その通りやってもらうって、実はデザインをお願いしてるわけ。
知らず知らずのうちに様々なデザインに触れているにも関わらず、かっこいいものだけがデザインとかって思われがち。政治、経済、医療、福祉、教育、ありとあらゆるところにデザインっていうのが必要であるし、実はデザインを通して人に届いてるのに、そう思われていないっていうところにちょっと課題は感じます。
デザインはいいけれども機能がちょっとねとかっていう言い方があるじゃないですか。それってデザインという言葉の使い方を間違ってるんですよ。機能も機能美のデザインなので。デザインというものが、ただ形とか格好とかっていうふうに受け取られてしまっている証なんです。そのぐらい誤解されている。
――大学のデザイン学科にはどういう思いで入ったんですか。
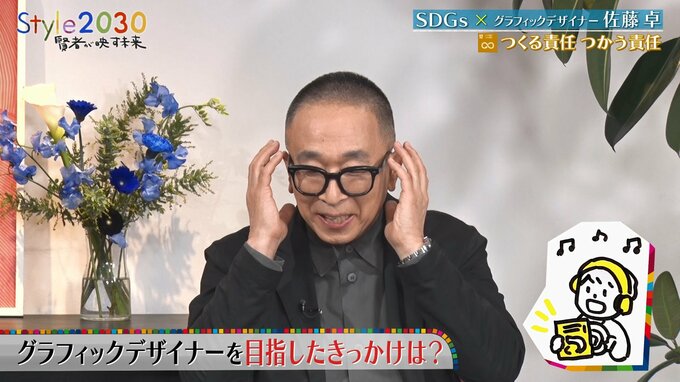
佐藤卓氏:
中学ぐらいからロックを聞き始めたんです。好きな曲をガンガンに聞きながら、かっこいいって思いながら見てるのはLPレコードのグラフィックなわけ。好きな音楽とグラフィックが繋がってるわけです。高校2年生ぐらいからそっち方面に行きたいなって思ったってことです。
――その頃の佐藤青年にとって、デザインはかっこいいものだったんですね。
佐藤卓氏:
あっ!そうか!いま気が付きました。入口はそうですね。














