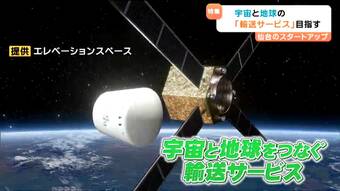図形は「解き方のバリエーション」を確認すべし
数学は、まず計算問題です。「スピードと正確性」を重視してほしいです。これくらい暗算でできるとか簡単だと思ってミスをしたり、問題を読み落とすことがあるのでスピードを意識しつつ、正確に解くことを繰り返すのが大切です。また、間違えたときは"ケアレスミス"という意識ではなく、次は間違わないようにと常に危機感を持つように。特に数学が得意な生徒ほど暗算でできるからと問題用紙に計算を書かずに解いてしまう。見直しの時のためにもちゃんと書いて正確にということを意識しましょう。
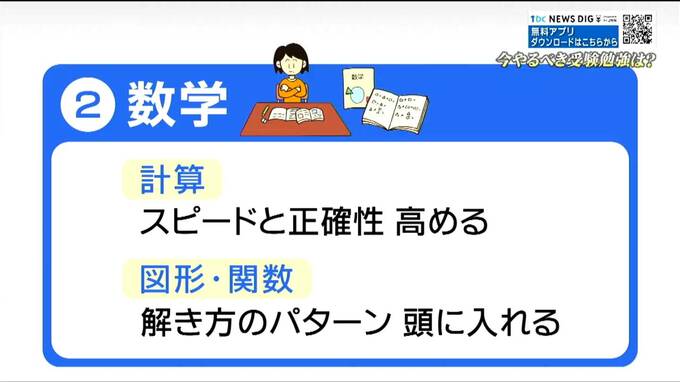
次に図形・関数です。ある程度「解き方のパターン」があるので、この問題が解ければいいではなくて、解き方のバリエーションを広げていってほしいです。一回解いただけだと定着しないので模擬テストや定期テストをもう一回解いてみてください。「解き直し」は効果があると思います。
Q、どの「解き方」をすればいいか問題を見るときのポイントは
例えば、図形の問題で「平行」「二等辺三角形」「中点」という言葉が出たとしまます。「平行」であれば、どんなことを思い出すか=角が等しい。とか一つのキーワードからどれだけ解き方を連想できるかが鍵です。数学の場合には、この解き方だと進めていって解けないときに違う考え方ができにくくなることが多いので、これじゃなかったらこっちの解き方だと、いろいろなパターンを常に頭に入れるのが重要です。
また、数学が苦手であれば「捨て問題」を作ることも大事かなと思っています。特に図形の最後の問題は、時間がかかる・難しい問題が多いです。そこで5分10分粘るのであれば、確実に点数が取れる第一問・第二問に戻って、絶対落とさないとそういう時間配分の練習もするといいですね。