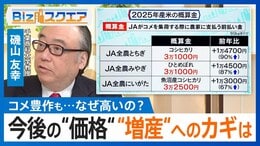「脂が劣化せず、刺身にも最適」与える餌で差別化などで広がる“ご当地サーモン”

上村キャスター:
注目を浴びているのが、国産のサーモンです。全国各地で様々なサーモンが登場していて、「ご当地サーモン」とも呼ばれています。
栃木県の「うつのみやストロベリーサーモン」は、県内のいちご「スカイベリー」を液状にして餌に混ぜるそうです。淡泊で上品な味がして、白身魚らしい弾力があり、日本酒にとても合うといいます。
北海道の「薬膳サーモン」は、松の実やオリーブオイル、きくらげなどを餌にしているそうです。脂分が少なくヘルシーで、業界初の「機能性表示食品」にもなっています。
与える餌によって、味や香り、栄養に違いを出して、新たな名産として売り出そうとする地域が増えているそうです。

「ご当地サーモン」は広がっており、水産研究・教育機構の調べによると、2019年12月時点では90種でしたが、2024年7月には139種にまで増えているといいます。
全日本サーモン協会のサーモン中尾さんは「冷凍しないので鮮度が抜群で、脂が劣化せず、刺身にも最適」と話します。
そして、国内産は輸送費も抑えることができるので「魚耕 荻窪本店」では、ノルウェー産のサーモンが799円/100gに対し、ご当地サーモンは390円~599円/100gと、3割から5割ほど価格を抑えることができるそうです。
井上キャスター:
養殖なので漁業権の問題もなく、餌や水質の管理ができれば安心安全に供給できますね。アニサキスなども排除していけるようになりますよね。
田中ウルヴェ京さん:
“持続可能な養殖”を考えると、食べている餌や育てられた環境を知ることができる透明性が必要になってくると思います。その面では、“ご当地ならでは”の情報を出していくことは重要ですよね。