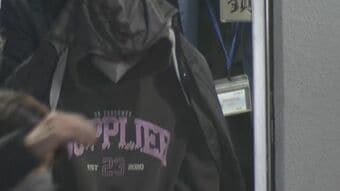100年目を迎えたNHK
さて、先に触れた通り、100年前の1925年に東京放送局(JOAK)の開局によって日本の放送がスタートしたが、これに続き、社団法人大阪放送局(JOBK)、社団法人名古屋放送局(JOCK)が次々と開局。翌年、この3局が統合して社団法人日本放送協会となる。この組織は、戦後、GHQが進めた放送制度改革の下で、その制度的位置づけを再定義されながらも、今日のNHKに引き継がれてきた。
そのNHKにとっても、放送開始から100周年を迎える2025年は、大きな転換点の年となる。
2024年5月、NHKが必ず行わなければならない必須業務に、これまでのラジオ放送、テレビ放送、放送に関する研究に加えて、インターネットを通じて番組などを提供することを加える改正放送法が国会で成立。これにより、NHKのインターネットを通じての番組提供業務が、受信料制度のなかに位置づけられることとなった。
この改正を受けてNHKでは、この10月から、テレビ受像機を設置せず、ネット配信のみでNHKのサービスを利用する場合の受信料額を、地上契約と同じ月額1100円とすることを発表している。もちろん、すでに受信料を支払っている世帯は、追加の負担なくサービスを利用できることになる。
他方で、前田晃伸・前NHK会長の下で行われたNHKのスリム化改革の一環として、ラジオ放送は、2026年3月末に、現在の3波から、「新NHK AM」、「新NHK FM」の2波に再編し、ラジオ第2で放送している語学などの教育番組は原則FMで放送することになると発表している。
デジタル化の波により、メディア環境の変化が激変するなかで、NHKにとって、インターネットを通じての番組提供業務の必須業務化は、NHKの将来に道を拓くために必ず行わなければならない重要な改革とと位置づけられてきた。
その検討が本格化したのは、2000年ごろからという。言わば、四半世紀に及ぶNHKの悲願でもあった。その意味では、インターネットによる番組提供業務の必須業務化は、NHKにとって、歴史的な転換点を迎えたことになると言ってもよいだろう。
もちろん民放局においても、動画配信サービスの普及の広がりやネット結線したCTV(コネクテッド・テレビ)が浸透する状況などを受け、TVerを共通ポータルとして積極的に展開しつつ、在京・在阪民放局を中心に、独自にオン・デマンド・サービスなど、インターネット上での番組/コンテンツ展開、ビジネス展開を進めてきた。この流れは、今年もますます進むであろう。
他方において、昨今、特に注目されているのが、インターネット上で提供される情報に含まれる偽情報・誤情報によるトラブルの急増であり、インターネット空間で、情報の信頼性をどう担保していくのかは、民主主義を標榜する西側先進諸国で共通する問題となっており、その方策が問われている。SNS等のインターネットを経由した情報への接触の急増により、フォルターバブル(※1)、エコーチェンバー(※2)といった偏食的な情報接触が、社会認識に対する分断を生む危険性が指摘されている。
※1 フィルターバブル
インターネットユーザーの好みを学習した検索エンジンなどのアルゴリズムによって、好みの情報ばかりが届くこと。また、そうした情報が「泡」のようにユーザーを囲んでフィルターのような働きをし、自分とは違う意見や情報に接しづらくなっている状態を指す。
※2 エコーチェンバー
直訳すると「反響室」。SNSにおいて、価値観の似た者同士で交流、共感し合うことにより、同じような意見や思想が増幅されること。
加えて、インターネット上を流通する情報接触の度合いが高まるなかで、信頼度の高い生活情報や社会情報が安定的に提供できる環境が求められている。その方策の一つとして、ネット空間で、より信頼性の高い社会情報の流通を促進するプロミネンス制度(※3)については、すでに西ヨーロッパの一部の国で制度化が進められている。
日本においても、2023年より、その制度的導入の可能性が総務省などで進められているが、2025年は、それらの論議がより活発化することが予想される。
※3 プロミネンス制度
プロミネンスは直訳すると「目立つこと、突出」。社会生活において重要で信頼性の高い情報を目立たせ、国民のアクセス機会を確保するため、表示の仕方など一定の措置を義務付ける制度。