「『6434』という数字が震災の被害に線を引いている」
上村彩子キャスター:
「遠因死」という言葉を今日初めて知りましたが、遠因死としてモニュメントに名前を残している方は何人くらいいらっしゃるんでしょうか?
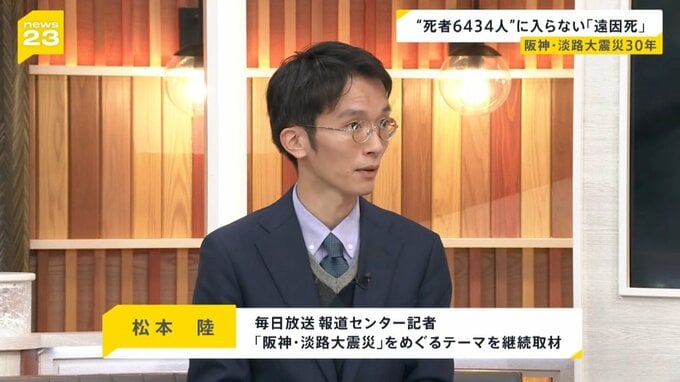
毎日放送報道センター 松本陸記者:
現在、このモニュメントには合計で5070人の方の銘板が掲げられているんですが、そのうち、「遠因死」で亡くなったとされる方の銘板は約300人にのぼります。
私自身、大阪のテレビ局の記者として阪神・淡路大震災の報道に関わる中で、毎年、死者6434人という数字を繰り返し報道してきたんですが、その無機質な数字が、この震災の被害に線を引いているというふうに感じてきました。
この大震災の爪痕の深さは「6434」という数字で語れるのか、その数字の外にいながらも人生を奪われた方々の悲しみや苦しみが見過ごされていないか。そういった疑問が、今回の取材を始めた原点です。
喜入友浩キャスター:
ただ「遠因死」という言葉はあまり耳にしないですよね。
松本記者:
現実的には、阪神・淡路大震災以外の災害で遠因死が語られることはあまりありません。例えば、その後の災害で自死された方が「関連死」として、認められるといった例も出てきてはいるんですが、遠因死の方を「関連死」の枠内に広く入れていくという状況にはなっていないと思います。
災害の死者を考えるときに、どこかで線を引くことは必要です。しかし、その線の中にいる人だけではなく、その外側や周辺にいる人々の悲しみや苦しみにも寄り添うことがメディアや社会には求められていると思います。

上村キャスター:
今回は震災30年という節目でしたが、どんなことを感じられましたか。
松本記者:
取材をしていても、年月の長さというのはかなり実感します。記憶の鮮明さや正確さという意味でも、かなり限界がきているという部分もありますし、生々しい記憶から歴史に変わっていくといった声も上がっているのは事実です。ただそれでも、震災で人生を奪われた方々の無念や、残された遺族の悲しみが完全に癒えることはないですし、繰り返しになりますが、そういった悲しみや苦しみに寄り添っていくことが我々には求められていると思います。
==========
<プロフィール>
松本陸さん
毎日放送報道センター記者
「阪神・淡路大震災」をめぐるテーマを継続取材














