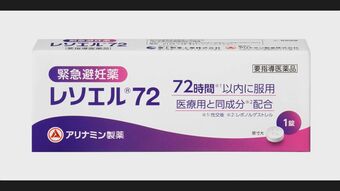2020年代の「子持ち様」批判
最近の子持ち様論争は、子どもの発熱などを理由に欠勤や早退をする人がいるという不満から広がった。もちろんこれには最近の社会状況も関わっていると考えられる。一つの要因として、SNSの普及があげられる。とくにXで、女性や性的マイノリティへのハラスメントが増え、匿名での誹謗中傷が横行していることも無関係ではないだろう。
もう一つの要因として、子育て世帯の減少があげられる。厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば、18歳未満の未婚の児童がいる世帯は、1986年は全世帯の46・2%であったが、2023年は18・1%と過去最低となった。
みんなが結婚して子育てをする時代ではなくなったため、自分に子どもがいないだけでなく親戚にもいないという人も珍しくない。子育てに対する理解が減ったうえに、結婚し子育てをする女性はそれだけで恵まれているという意見もみられる。
ライフスタイルの多様化が進む一方で、子どもがいる、子育てをする人だけに育児休業などの休みがあるのは不公平になる。業務負担が増えた人に手当を支給するなどの仕組みが必要だ。また、勉強や留学、他の目的でも休みを取れるようにしなければ職場の雰囲気が悪くなる。職場マネジメントの改善が欠かせない。
しかし、このような休業や職務に関する仕組みを改善したとしても、公的な場に子育てを持ち込むなという批判は形を変えて起こり続けるだろう。誰でも子育てしやすい社会を築くには、会社のマネジメントだけでなく、ケアに関わる制度や意識、性別分業を根本的に変えていく必要があるのだ。