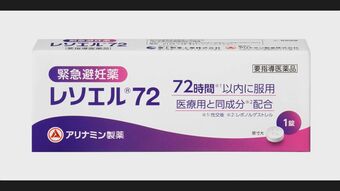ケアに満ちた社会へ
人の命を預かるにもかかわらず、なぜ育児や介護などケアの価値は低いのだろうか。岡野八代(2024)によれば、政治こそが、何が無償で行われるべきケアであり、有償で行われる場合にはケアの報酬を決めることでその社会的な価値を決定してきた。
ケアの責任の割り当てを長きにわたって女性に押しつけてきた政治そのもののあり方が問われるべきであるという(※2)。そうであれば、政府や企業は長時間労働の解消をいっそう推し進め、男性もケアを担えるように制度を整え、女性に偏る負担を減らすべきだ。
また、最近の子持ち様論争は、男女の賃金格差とも深く関わっている。厚生労働省「2023年賃金構造基本統計調査」によると、フルタイムの一般労働者の平均賃金は男性が月額35万900円、女性は26万2600円である。経済協力開発機構(OECD)の調査では、主要7カ国(G7)の中で日本が最も男女の賃金格差が大きい。
子どもが病気になったら、保育園は預かってくれない。当日に病児保育を見つけるのも難しい。筆者らの調査では、子どもが病気になったとき、賃金および昇進の見込みが高い夫の仕事が優先され、賃金および昇進の可能性がより低い妻の方が仕事を休む戦略が採られる傾向がみられた(※3)。
子育てで休むのは母親が多くなり、女性たちが「子持ち様」として批判される要因になっている。この状況を変えるためには、男女間の賃金や育児分担を平等にすることが求められる。さらに、経済的に豊かでなければ望んでも結婚や子育てをしにくい状況を改善する施策も必要だ。
こうしたケアをめぐる制度や意識の改革、ジェンダー不平等の解消がなければ、子育てをする女性たちへの批判の歴史は繰り返すだろう。国は産めよ、育てよ、働けよという「女性活躍」を推し進めてきた。だが、少子化を嘆く政治家は多い一方で、子どもを必死に育て働く母親に批判が集まる状況を嘆く政治家は少ないようだ。そんな国で子どもが増えると思いますか。
(※1)溝口明代・佐伯洋子・三木草子編『資料 日本ウーマン・リブ史Ⅱ』松香堂、1994年.
(※2)岡野八代『ケアの倫理――フェミニズムの政治思想』岩波書店、2024年.
(※3)額賀美紗子・藤田結子『働く母親と階層化――仕事・家庭教育・食事をめぐるジレンマ』勁草書房、2022年
<執筆者略歴>
藤田 結子(ふじた・ゆいこ)
米国コロンビア大学大学院で修士号(社会学)、英国ロンドン大学大学院で博士号(コミュニケーション)を取得。明治大学等を経て2023年に東京大学大学院情報学環に着任。米英と日本で、メディアと国際移動、人種・ジェンダー、労働などをテーマにエスノグラフィー調査を実施。
著書に『文化移民―越境する日本の若者とメディア』(新曜社、2008、第2回内川芳美記念マス・コミュニケーション学会賞受賞)、『ワンオペ育児』(毎日新聞出版、2017)、『働く母親と階層化―仕事・家庭教育・食事をめぐるジレンマ』 (共著、勁草書房、2022)他。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。