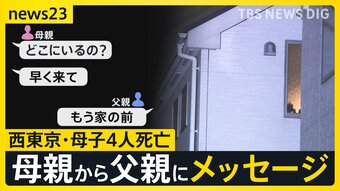日銀の金融政策報道に反省点
支局長を務めた10年間、年に8回ある日銀政策決定会合の報道に力を入れていた。2025年1月現在のように、政策変更が予想される時は特にそうだったが、はたしてそれほどの意味があったのか。
日本の報道機関も日銀の動きに敏感で、日銀総裁の単独インタビューともなれば、大々的に一語一句を分析する。読者や視聴者には「よくわからない組織だけど、どうやら微調整だけでも我々の生活を大きく変えるすごい力のある機関」との印象を与える。こうしたイメージには妄信の部分があるのではないか。
アメリカの中央銀行に当たるフェド(FRB)でも、2022年から大幅に金利を引き上げたのに、大方の予想に反して景気をそれほど冷え込ませなかった。中央銀行報道の在り方に疑問を持つようになった。
財政もそうだ。数年前、大手一般紙の名物編集委員と当時のツイッター上で短い論争になったことがある。財政破綻が間近で早く増税などをしないと大変なことになるんだと不安を煽って四半世紀が経っているのに、その危機はなかなか来ないのはなぜか。来なかった理由をまともに検証しないでやたらに同じ論調を繰り返すのはいかがかと指摘したところ、「警鐘を鳴らすのが記者の仕事だ」という答えが返ってきた。
なるほど、お立場は理解するが、やはり検証が必要だと思う。シェアード氏に言わせると、「国の“借金”は廃止すべき表現。国債を返さなければいけない借金だというとらえ方をすべきではない」。ちなみに、私たちが持っているお札もバランスシート上、日銀(つまり政府)の負債になっているが、一般の人は財布に政府の借金が入っているという感覚はないと思われる。
日本円の国債だから、政府・日銀は国債償還のためにいくらでも円は作れる。過剰に作るとインフレになる恐れはあるので、財政規律を重視する論調も間違ってはいないが、税収が足りないから日本がいずれ破綻するだろうという見方には根本的な誤解がある。もう少し早く気が付いていればよかったと思っている。
以上の著書がすべて正しいとは言わないが、一方のとらえ方しか伝えない日本のマスコミに問題がありそう。「財政健全化への努力を止める余裕はない」(日本経済新聞、2024年12月1日付社説)といった一本調子の論調を何十年も続けていればオオカミ少年と見られるようになり、読者の信頼を失う恐れがある。
一方、日本の年金資産を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)もマスコミに誤解されている部分があると思う。約250兆円の資産を持つGPIFの大きさゆえに、支局長在任中、何回か取り上げたが、将来の年金を支払うために株式と債券の運用益で財源を確保するというGPIFの表向きの存在理由を私も鵜呑みしていた。
しかし、考えてみたら円で支払う年金だから、政府はいくらでも円は作れる。問題は財源があるかどうかではなく、年金で生活する高齢者が受け取った円で生活の必需品やサービスを買えるかどうかだ。GPIFの運用実績にかかわらず、日本の現役世代がこれらを生産したり、輸出で稼いだドルで輸入して調達したりすることさえできれば、大丈夫なはずだ。昨年中、そういう見方もあるのだと気づき、もっと早く記事に反映できればと考えている。