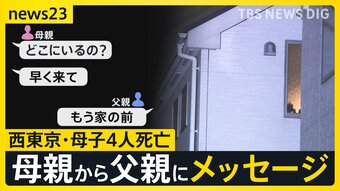アベノミクス初期に東京支局長に着任
私が1999年に入ったウォール・ストリート・ジャーナル紙は政治と外交、たまには大谷翔平やテイラー・スウィフトまでもカバーする新聞ではあるが、中心は経済、企業、金融の報道。支局長の10年間を振り返って、これらの分野に重きをおく。
雪の降る東京に着いた2014年2月11日、経済低迷が続いたとされる「失なわれた20年」を挽回しようと、安倍首相(当時)が掲げるアベノミクスと黒田バズーカが始動していた。アベノミクス三本の矢の一本目は大胆な金融緩和。2年で2%インフレを達成し、デフレ脱却と持続的な経済成長を目指す日銀の黒田総裁に注目が集まり、私もその政策の理解に腐心した。
当時私は経済学者のポール・クルーグマン氏の信奉者で、社内で「360度評価制度」の一環として部下が私を匿名で評価したところ、「支局長がクルーグマンを引用しすぎている。やめてほしい」との回答がでるほどだった。
「中央銀行が無謀な計画を約束するのがデフレ時代にむしろ効果的」というクルーグマン氏が1990年代末に示した理論に沿って、15年後の黒田総裁が無謀と思われる国債購入計画を進めていた。日銀が毎年80兆円程度の国債を購入し、経済に現金をじゃぶじゃぶ入れる政策で、ハイパーインフレと国債の不履行(デフォルト)を引き起こすと予言する人もいた。
しかし、そうした悪影響もなければ、目立った効果も出なかった。消費税増税が景気に打撃を与える中、焦った黒田総裁がマイナス金利の導入や国債金利のくぎ付けに踏み切る。こちらの効果も限定的。早くもクルーグマン氏が2015年11月、「日銀が自力でインフレを引き起こすのが難しい」と立場を修正した。
途方に暮れた私は日銀のバランスシートを調べたり、お金とは何かを考えたりする中、異端の学者やエコノミストたちにたどり着いた。その一人が知日派のポール・シェアード氏で、彼の“The Power of Money(お金の力)”(2023年、邦訳今年6月出版予定)やステファニー・ケルトン氏の“財政赤字の神話”(邦題、早川書房2022年)を読んで目からうろこが落ちる思いがした。
シェアード氏によれば、国債とお金(例えば私たちが銀行に預けている預金、または銀行が日銀に預けている当座預金)には大きな違いはない。日銀は政府の一部で、当座預金は日銀(政府)の負債だから、黒田バズーカにあったように日銀が一般銀行から国債を買って代わりに当座預金を増やしても、同じようなものを交換しているだけで、大した効果は期待できないという。2010年代に実際に起きたできごとを理論面で支えている。
必ずしも定説になっていないこれら主張の詳しい説明は本や学会の論争にゆだねるが、経済報道を担当するものとして、いくつかの教訓や反省点がある。