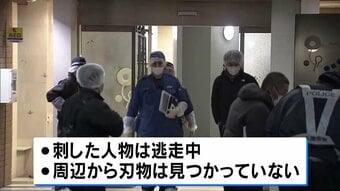「103万円の壁」の減税額はわずかに
国民民主党が主張した「103万円の壁」の問題、最終決着は来年に持ち越されました。ただ、自民・公明の与党は国民民主党を押し切る形で123万円に引き上げることを決め、予算案を編成しました。基礎控除と給与所得控除をそれぞれ10万円引き上げて、壁を103万円から123万円に引き上げるとしています。
このうち給与所得控除については、年収によって控除の限度額が決まっているので、今回の引き上げの恩恵を受けるのは、年収190万円までの人だけです。それ以外の人には影響しません。
基礎控除の10万円引き上げは、年間の課税所得が2350万円未満の人にはすべて減税になりますが、減税額は課税所得額が330万円未満の人年間1万円、695万円未満で2万円、高所得層の1800円以上2350万円未満の人でも4万円となっており、国民民主党の当初の主張である「すべて基礎控除で178万円まで引き上げ」という案に比べれば、減税額はかなり小さくなりました。
しかも、2025年の年末調整で対応するということなので、12月まで税金が戻ることはなく、景気刺激効果はあまり期待できないと言って良いでしょう。家計支援、景気下支えのための減税であれば、もっと早くやった方が良いのですが、そもそも「壁引き上げ」という言葉が、就業促進のためなのか、物価調整なのか、景気対策なのか、目的の曖昧さを残していたため、詰めた議論に至らなかったと言えるでしょう。
税収は過去最高の74.4兆円見込む
政府案による「103万円の壁」の減税規模(税収の穴)は、総額7000億円で、今のところ、財源は明示されていません。ただ、来年度予算案では税収が過去最高の78兆4400億円と見込まれており、7000億円であれば、税収の大幅増加によって吸収できるという計算なのでしょう。
名目の賃金、物価の上昇で、所得税も、法人税も、消費税も軒並み上振れ、今年度当初予算に比べて8.8兆円、補正後と比べても4兆円も税収が増えるというのに、インフレ課税に苦しむ家計に「還元」するという議論にならない政策決定プロセスは、魔訶不思議です。
来年度予算案の衆議院通過にあたって、2月に大詰めを迎える「103万円の壁」の攻防では、国民民主党が求める上積み額に注目が集まることでしょう。しかし、過去の消費税増税や、今の物価上昇にも関わらず、所得税の改革が長年手つかずになっていることを考えれば、「壁」の話に終わらせず、所得税の税率や刻みなど所得税の抜本的な改革の議論につなげることも重要に思えます。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)