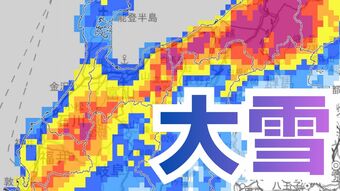■ゴルバチョフ氏の死は「ロシアの自由主義の死」を象徴
「ゴルバチョフ氏がウクライナ侵攻の最中に死んだということは、ロシアの自由主義が死んだということを象徴している」とみる研究者もいる。時事通信社でモスクワ支局長、外信部長などを歴任した名越健郎・拓殖大学特任教授だ。

ゴルバチョフ氏は、ペレストロイカ(改革)やグラスノスチ(情報公開)を進め、西側諸国から歓迎された。ところが、ロシア国内では真逆の評価が定着している。
「自由とか民主主義とかで膨大な功績があったと思うが、ロシア人には受けなかった。西側にとっては、『功』のほうが多いが、ロシアとしては『害』ということ」
名越教授は、ゴルバチョフ氏が国民に受け入れられなかった大きな理由として、経済政策の失敗を挙げる。「当時私も現地にいたが、深刻な物不足だった。経済がダメになったのでソ連は崩壊した」と振り返る。
対比して挙げたのが、現政権を握っているプーチン氏だ。名越教授はプーチン氏が支持される理由として「2000年代になり、原油価格が高騰し、短期間で消費社会が実現できた。ロシア人が史上初めて消費社会を得たということ。それが続いているからプーチン氏が支持されている」とみる。
名越教授が着目しているのが、国民の70%がウクライナ侵攻(ロシアでは「特別軍事作戦」)を支持しているという以前の世論調査だ。「30年でこういう国に劣化してしまい、国民が愚民化してしまった。マスコミに一番責任があり、それを放置して許している。政権が怖いというのもあるだろうが、(ゴルバチョフ氏の死は)ロシアの自由主義の死ということで象徴的だ」
■「ロシア人を分かっていなかった」ゴルバチョフ氏
ロシアがゴルバチョフ氏の目指した西側諸国との“融和”から遠ざかっていったのはどうしてなのか。毎日新聞の記者として2度のモスクワ特派員経験を持つフリージャーナリストの石郷岡建氏は「ゴルバチョフ氏はロシア人の気持ちを分かっていなかった」と指摘する。
「一般的なロシアの人からすると、ゴルバチョフ氏はペラペラ喋るがほとんどまともなことはせず、ロシアをめちゃくちゃにしたという意識が非常に強い」
ペレストロイカで社会主義体制を改善しようと試みたが、ソ連は崩壊。人々の暮らしもさらに厳しいものになり、人心は離れていった。ソ連崩壊から5年後の1996年、ロシア大統領選でのゴルバチョフ氏の得票率はわずか0.5%だった。
石郷岡氏が象徴的な事件として挙げたのが、1990年にモスクワで行われたゴルバチョフ氏とアメリカのベーカー国務長官との会談だ。この中でベーカー国務長官は「米軍がNATO(北大西洋条約機構)の枠内でドイツ駐在を維持することができるのならば、現在のNATO軍事管轄範囲から1インチといえども東方方向へ拡大することはない」と語ったとされる。しかし、正式な合意文書は作られず、NATOはその後、東方に範囲を広げていく。ロシア人からみると「ゴルバチョフはだまされた」ということになる。
「共産党に乗っかりながら、ベーカーに経済などで助けを求めたゴルバチョフ氏に対して、ロシア人は『みっともない』という思いが非常に強かった。逆にプーチン氏については『ロシアに恥をかかせるようなことをしていない』ということになる」