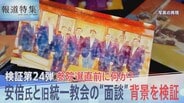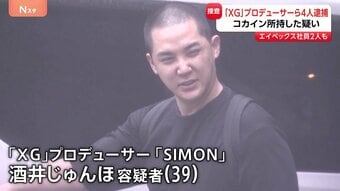宗教団体「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)」は9月21日、報道機関に対して「教会改革推進本部」を設置することを明らかにしました。22日には就任した勅使河原秀行本部長が記者会見を開き、各報道機関からの質問に応じました。 同席した福本修也弁護士も回答に応じる中、時折応じる口調が強くなる場面も・・・
注目の会見を全文ノーカットでお伝えします。
■恨みを買うことはあってはならないこと 宗教としての根本的なあり方について議論を重ねた
勅使河原秀行本部長:
本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。
私は世界平和統一家庭連合で、教会改革推進本部を担当することになりました。
勅使河原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに今回の安倍元首相の銃撃事件以降、様々な報道を通じて、世間を大変お騒がせしましたことを、並びに日本国政府、そして国会議員の皆様に、大変なご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。
改革案の説明を始める前に一言申し上げたく思います。
あくまでも個人的な思いでありますけれども、今回の容疑者である山上徹也氏のお母さんが、以前に家庭連合に入信した際、多額の献金をして、それがゆえに、家族が不幸になったと。家庭連合に対して恨みを持ち、その家庭連合に対する恨みが、今回の犯行の動機であると話していることを聞いて、私は大変胸が痛みました。
また一連の報道を通して、日本国政府が調査に乗り出すという事態にまで招いていること。そして、国会議員の先生方が、1人1人当法人との関係があったか、なかったかということで、メディアから1人1人詰問されるような、そういった事態を招いていることを、大変申し訳なく思っております。
さらに、元信者と言われる方々が、テレビや週刊誌に登場して、家庭連合との関わりにおいて、過去に起きたつらかったこと、あるいは苦しかった体験を告白されていますけれども、
そういった姿を見ても、大変申し訳なく思っております。
本来、公共の福祉に資するべき宗教法人が、例えたった1人であったとしても、恨みを買うということはあってはならないことと存じ上げております。そういった観点から、田中会長はじめ、責任役員並びに、スタッフ一同が、この2か月半にわたって、この家庭連合、宗教としての根本的な法人のあり方について議論を重ねてまいりました。
そして21日、その改革の骨子に関しては、プレスリリースさせていただきました通りです。これからそのプレスリリースの内容に関して、順に一つ一つご説明させていただきたいと思います。
■「献金は感謝の表れ」「過度な献金にならないよう配慮」2009年に発表した改革内容を再度徹底
まず、改革の方向性として、大きく3つ挙げさせていただきました。
1つ目は2009年に既に発表しましたコンプライアンス宣言の指導の内容、これを徹底させる、再度徹底させるという意味であります。
第1番目が民事裁判等で問題とされたような献金と、先祖の因縁などをことさらに結びつける。または、威迫困惑を伴うような献金奨励、勧誘行為はしてはならない。ということであります。
本来献金というものは、信徒さんが神様に出会って、そして神から愛されているという実感を通して、喜びと希望を持って、その感謝の表れとして捧げるものであります。従いまして、いかなる理由があったとしても、人に不安を与えたり、あるいは怖がらせるような献金の集め方は、決して許されるものではありません。
様々な事情があったとしても、それは当法人の一貫した考え方であります。このことは再度徹底いたします。
2つ目に、信者への献金の奨励・勧誘行為は、あくまでも信者本人の信仰に基づく自主性および自由意思を尊重し、信者の経済状態に比して、過度な献金とならないよう十分配慮しなければならない、であります。
献金は先ほど申し上げたように、感謝の表れであると同時に、ひとたび神の実在を知って、そして神様と人類のためにという、家庭連合の教義においては、他のために生きるという教えがありますので、その観点から、より公的な意味で献金を捧げるという意味合いがありました。
この考え方は、尊いことであり、その考えに基づいて信徒さんが献金を捧げるということは、我々としては尊い行為だと考えております。しかしながら、その献金がある意味度がすぎて、その家庭やご家族の生活を、通常の生活を送ることを害するような、そういった過度なものになってはいけないということは、当然のことであります。従いまして、この観点に関しても今後十分に指導していきたいと考えております。
3番目は、伝道活動において、勧誘の当初から家庭連合であることを明示することであります。
家庭連合は正体を隠す理由は何もありません。従いまして、正体、家庭連合であるということをしっかりと明かすというのは、一貫した指導であります。
この3点でありますけれども、これはもう13年前の2009年に指導開始した内容であります。では、この指導の効果があったのかなかったのかということで、少し時間をいただきたいと思います。