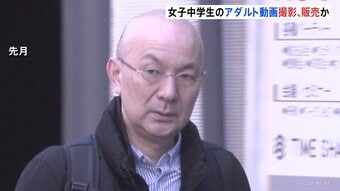やはり本は生きる力
コロナ禍前のことになるが、こんな光景もあった。近隣の幼稚園や保育園、子ども園には、外国にルーツを持つお子さんがたくさんいらっしゃる。ある幼稚園では、10人から20人ぐらいのお子さんたちが、先生と一緒にお散歩を兼ねて当館を訪れる。
その時は、図書館の職員が絵本を2冊ほど読み聞かせをして、その後、お子さんたちはひとり2冊まで好きな本を借りていく。みんな思い思いの本を借りていく。韓国のお子さんは、韓国語で書かれた絵本を。中国のお子さんは、中国語の絵本。ベトナムのお子さんは、ベトナム語の絵本というように。ニコニコして、いそいそと借りていく。
ある時、外国人のお子さんが、小学校3、4年生レベルの日本語の本を選ぼうとしていた。不思議に思った先生が「あなた、まだこの本、読めないでしょう?」と聞くと、「これは、おかあさんのために、かりるの」。
おそらく、この子は、日常生活でお母さんが日本語で苦労している姿を目の当たりにしているのだろう。なんとかお母さんの力になりたい、喜んでもらいたいという気持ちから、自分が借りたい1冊を我慢して、その本を選んだのだと思う。「まあ、あなた、なんていい子なの!」と先生。わたしも傍らでこの光景を見ていて、思わず目がうるっと来た。
そう、本は間違いなく、国境を超えて、国籍を超えて、様々な形で、人それぞれにとって「生きる力」となっているのだ。
図書館は安全地帯
日曜日になると、いつもお父さんと一緒に来る、小さな外国人の女の子をよくお見かけした。とにかくお父さんにくっついて離れない。この子はお父さんのことが大好きなんだろうと、端から見ていてもすぐにわかる。お父さんは、いつも女の子と一緒に絵本を読んでいる。
いつだったか、お父さん、くたびれてしまったのだろう。うとうとし始めた。すると、女の子は女の子で、お父さんの傍ですやすやと眠っている。お父さんの傍というだけで、安心しきっている寝顔だ。その時は、周りにあまり人気もなかったので、そっとしておいた。
そう、図書館は「ホッとできる場所」なのかもしれない。