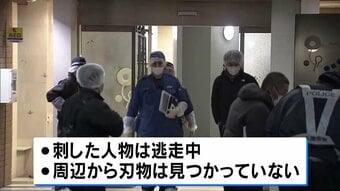年代が下がるほど、投票先は「当日」に決めた 侮れないネットワークも
前回2021年の衆院選で投票する候補者を決めた時期について、公益財団法人「明るい選挙推進協会」の調査によると、「投票日当日」と回答した70歳以上の人は4.6%だったが、以降は年代が下がるごとに割合が増えており、18~29歳は32.9%の人が「投票日当日」に決めたと回答している。
中央区・晴海に住む会社員の男性(47)は「子どもの保育園の友達の保護者以外、マンションの近隣住民との交流はほぼない。エレベーターで挨拶するくらい」とし、「衆院選?もちろん行きますけれど、候補者の人は見たことがない。選挙公報を見て決めます」と話す。

他方、2024年の東京都知事選挙では、「晴海西小・中学校」の投票所で投票率74.64%を記録したように、しっかり投票に行く意識がある地区だ。
XやInstagram、YouTubeといったツールを駆使して、街頭で会えない有権者に声を届けようとする候補者も多かった。ただ、インターネットは幅広い層にアプローチできる一方で、自分の選挙区の有権者だけに届けることはできず、能動的に情報をとりにくる人にしか訴えられないデメリットもある。
「意外とママ友・パパ友のネットワークは侮れない。地方の選挙のように口コミが有効なこともある」と語る陣営もあった。しかし、中央区・勝どきに住む会社員の女性(33)は「保育園の知り合いと選挙の話はしないし、何か投票をお願いされたこともない」と打ち明ける。

10月27日に投開票された衆院選は、東京2区も3区も組織票を固めた自民党の候補が当選した。ただ、町会・自治会の加入率は品川区で58.3%(2020年4月時点)ほどで、町会・自治会の役割が大きく影響した、といったことはなさそうだ。候補者の打った手の何が投票の決め手となったか、今後調べてみたい。