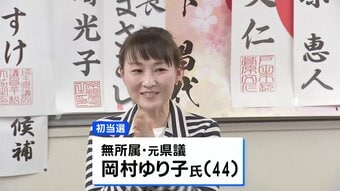物価に追いつかない賃上げ 「好循環」3年目の試練

「特売」の減少は、良い兆候なのか。本当に「実質賃金」は増えているのだろうか。「名目賃金」と「実質賃金」の推移グラフ。「実質賃金」に注目すると、2024年5月まで26か月連続でマイナスだった。6、7月は「ボーナス月」ということで、プラスになったが、8月は再びマイナスになっている。
――物価が上がることは経済にいいと聞いても、賃金が追いつかないと「好循環」といえない。追いつかない「悪循環」ではないかというのが、人々の率直な気持ちだが、本当にいい方向に向いているのか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
「名目賃金」の推移をみると、一番最近(2024年8月)は3%。春闘で5%ぐらい上がったが、そのうちのベアの分が約3%。ちょうど数字としても毎月勤労統計に表れてきている。連合など組合に参加されてない人も含めて平均的には3%と非常に高い水準で上がっている。そういう意味では「名目賃金」も好循環の良さが出てきている。問題は物価との兼ね合い。「実質賃金」は厚労省の数字なので、見方が難しいが、今の足元は大体2%。そうすると3%の「名目賃金」で、物価が2%だとすると1%ぐらいは上がっている。別にずっと前から上がっていたわけでなく、ごく最近の数か月がそうなっているだけの話。そういう意味では少しずつ良い方向にいっていると思う。
――「実質賃金」を上げるためには、「名目賃金」を上げる方法と、物価を下げる方法がある。今回の選挙の中では「物価を下げてくれ」という圧力が強い。それでも「物価を下げる」より「名目賃金を上げる」方法をとった方がいいのか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
日本の問題は、物価が高いことではなくて、賃金が低いことだと思っている。なので物価が高いことは一旦放っておいて、賃金の方が何とかなるように頑張るというのが王道だ。ただ前回の参議院選もそうだったが、選挙になると必ず「物価を抑える」となる。実は、物価を抑えることは実は海外でも非常に評判の悪い政策。例えばヨーロッパはウクライナに近いせいもあってエネルギー価格が、日本より上がった。その彼らの国々でもエネルギーの価格を抑えるというのは半年間ぐらいやっただけで、2022年の年末には終わらせている。それはあまりにも「物価を抑える」方向の介入のデメリットが大きいと彼らは自覚しているから。しかし残念なことに、日本だけ未だに続いている。しかも先々も続きそうなので、どこかで価格を抑えるのではなくて、「弱い賃金」をもっと強く押す政策という方向性に大きく変える必要があるのではないか。
――ようやく「名目」で「賃金」と「物価」が上がった。さらに「実質」が増えるようにしたいということか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
「名目」で「物価」もそこそこ上がってきた。それから「賃金」も上がってきた中で、多くの人は「これが普通。嬉しくはないがこういうものだ」という認識を持ってきているようになっている。それから企業の方もかなり自由に自分の価格が動かせるという自信を深めているので、積極的に投資をして新しい商品をつくって、少し高い値段でしっかり儲ける企業も出てきている。やはりそれは経済全体のダイナミズムというものをつくっていく、まさにこれが「好循環」のターゲットだった。そういうものが始まってきている。

春闘の賃上げ率。2023年春闘でも久々の3%台が出た。24年は5.1%。25年は同じ5%以上目標で、しかも中小企業については、1%プラスして6%以上と、中小の方が高い要求を掲げる。
――この内容に対する評価は?
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
2024年も目標は5%以上だったが、同じものを掲げているというので妥当だと思う。中小企業については、2024年の春闘でも健闘していたが、それでも大企業に見劣りするのは間違いない。そのギャップをきちんと埋めていこうと。賃金の水準そのものがどうしても中小企業だと低い。それを少しでもいいから大企業に近づけていこうというのが5%と6%という目標数字の違いに表れているし、それも必要だと思う。
――「名目賃金」を上げていく上でやらなければならないことは何か?

東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
日銀の話がよく出てくるが、実は日銀がやれることは非常に限られている。実際にこの何年間も日銀が賃金絡みで「頑張れ」とは言うが、日銀自体がやったことはない。一方で政府がやるべきこと、やれることはずいぶんあり、一つが「最低賃金」。2023年の岸田政権のときに諮問会議に一時的に参加したが、2023年に「(最低賃金)1000円にしよう」という話をして、そのときに「10年ぐらいかけて(最低賃金)1500円というのを考えたらいいのではないか」という議論をした。それを総理が2023年の夏にアナウンスをした。
――それと、あとは下請け問題か。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
中小企業の厳しいところは、親企業がどうしても「うん」と言ってくれない。賃金を上げたい、だけどそれには価格を上げなければならない。そのとき親企業がイエスと言ってくれなかったらできない。その“親子関係”の歪んでいるところを今直そうとしている。この主体は実は独占禁止法であり、公正取引委員会で、政府の中の一部署。厚労省が中心に決めている「最低賃金」と、それから公取が決めている下請け絡み。この2つが大きな好循環への最終的なステップだと思っている。
――3年目の賃上げが本当に実現できるか。いよいよ正念場だ。
(BS-TBS『Bizスクエア』 10月19日放送より)