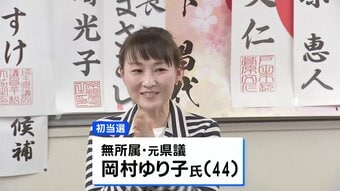賃上げ効果で再び物価上昇 「賃金と物価の好循環」3年目

東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
民間のエコノミストが翌年のインフレ率を予想したグラフ。2021年9月の時点で「22年度はどうなるか」という予想してもらったところ、ピークは「0.6%」ぐらいだった。場合によっては「0%」という人も何人かいるぐらいの感じで、当時はまだエコノミストたちの予想が低かった。ただ時間を移動するにつれて、だんだん右側(上昇)に分布が移ってきている。一番新しいのが2024年9月に「25年度はどうなるか」と予想したもの。「2%」としているが、かなりピークが近くなってきており、まだばらつきが少し残ってるとはいえるが、それでもかなり分布がタイトになってきている。日銀がよく「2%の周辺にアンカーされる」というが、そこに近づいてきていることをうかがわせる。
――「2%」「目標達成」とまではいかないが、それに向けて少しずつ近づいてることは間違いないということか。しかし「賃金が追いつかないから困る」という声も強くなっており、2024年10月の衆院選では物価高対策など経済政策が争点の一つとなっている。
国民が苦しむ「物価高」 各党の経済政策は…?
今回の衆院選で与党の自民党・公明党は、電気ガス料金などの支援に加え、低所得者世帯への給付金を訴えている。
立憲民主党は「分厚い中間層の復活」を掲げ、中低所得者の底上げに向け、税制の見直しを訴えている。
その他の野党は減税の主張が目立つ。日本維新の会は消費税8%への引き下げ。
共産党は、消費税は当面5%にし、将来的には廃止。国民民主党は、実質賃金が持続的にプラスになるまで5%への引き下げを掲げている。
れいわ新選組は「消費税廃止」。社民党は「消費税3年間ゼロ」。参政党は「積極財政と減税」を訴えている。
そして、多くの政党が掲げているのが「最低賃金1500円の実現」。しかし、原材料費や光熱費の値上がりで利益が圧迫されている企業にとっては、人件費の増加は簡単なことではない。

日本商工会議所 小林 健 会頭:
最近賃金でしか払えない企業が、今の地方の産業・商業インフラを担っている。インフラを担っている人たちが退出してなくなってしまうと、地方そのものが、瓦解の危機に陥る。