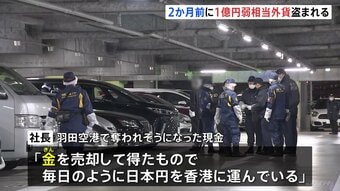2023年夏から物価に弱さ スーパー店頭価格に異変

9月の消費者物価は「生鮮・エネルギー」を除く総合指数で「2.4%」。日銀が目標とする「2%の物価指数」は2年半ぐらい超えた状態だが、消費者はもっと上がっている実感がある。食品、飲料、日用雑貨などをスーパーで店頭販売している商品のPOSデータに基づく価格上昇率の推移をみると、2023年9月には上昇率「9%」を超えていたが、実はその後、下落していて、10月8日時点で「2.65%」となっている。
――こちらのデータの方が普通の人の物価の感覚に近い。ここから何が読み解けるのか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
まずは2023年の夏にかけての上昇は、食料品メーカーなどが、積極的にコストが上昇した分を価格転嫁していった。実際にメーカーに聞いてもかなり積極的にやって「おなかいっぱいに転嫁した」みたいなことを言う人もいる。その後、価格自体は下がっていないが、上昇率が(前年比で)徐々に下がってきている。一つには輸入物価の転嫁が一巡した。それから消費がどうしてもなかなか振るわない。2023年の春闘はそこそこ良かったが、多くの人は「賃金がしっかり上がった」とはならなかったので、いま上昇率が徐々に下がってきた。
――データを見て「売れない」「売れ行き落ちたと」なれば、特売や値下げをするのか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
非常に良いのは、特売とか通常価格とか全部のことがわかるので、それを合わせた価格が今のような動きをしている。

スーパーの特売が物価に与える影響を表したグラフを見ていく。特売が多く、結果的に物価を押し下げている状況。しかし2024年9月以降は特売が減り、価格を押し上げている。
――2024年に入っては、「物価の下押し圧力」が強かったのか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
前年同月比で、特売が増えている。あるいは特売のディスカウント幅が大きくなることがずっと起きてきた。
――2024年の前半からいまに至るまでは消費の現場が弱くて、価格の上昇圧力が弱かったということか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
特売に注目している。スーパーの店頭の売れ行きをよく見た上で価格を上げたり下げたりしなければならない時に、通常価格は動かしにくい。特売は比較的臨機応変にできるので、(このグラフは)非常にうまく表している。
――ただ、2024年の前半は円安が急速に進んで、再び物価上がってきたのではないか。そこは実態とは違ったということか。

東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
2024年の円安の時期に特売が増えていた。スーパーは特売を増やして価格を抑えてきた。その結果として、円安は進んだが、我々の指標はむしろ下がっていくという逆方向の動きが起きた。
――これまで円安が進むとスーパーの店頭価格も上がっていたが、2024年は円安は進んだが、スーパーの店頭価格は大きく下がった。それだけ需要が弱かったということか。需要が弱い時期だから日銀は利上げを2回やったのか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
2024年に入ってから利上げしたので、インフレ率が下がってくる局面で利上げをした。
――「2%の物価目標」があり、日銀は「持続的・安定的ではないといけないから、名目賃金が2%を超えても目標達していない」としている。2%という目標への距離はまだある状況なのか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
物価2%までの距離はある。例えば1年後、可能性としては「消費者物価指数(CPI)が良くない」あるいは、2026年春闘の話も出るかもしれないが、「賃上げ難しそう」という可能性など、何かしらあると思っている。そういう意味では「2%」がしっかり定着しているとはいえないと思う。
――植田総裁が言っているように「円高・円安」「資源高」といったコストプッシュ型の物価の上昇は強いけれども、まだ自律的に物価が上がっていくような感じではないのか。
東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺 努氏:
大きく言うとそうだ。実際には輸入物価だけではなく賃金も上がっていて、国内要因による転嫁も進んでいるので、必ずしも輸入物価が全部ではないが、国内物価の分も含めてすごく強い状況で、(達成確実で)万々歳とまではいっていない。