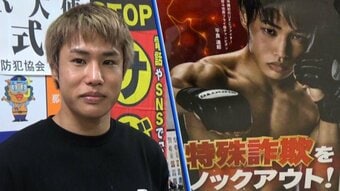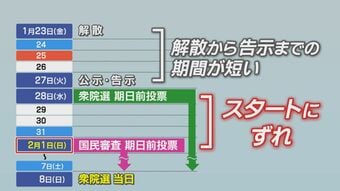仮設住宅が建った用地をもとの用途別にみると、63%が元々住宅に使えるように開発された土地で、インフラもあったという。このうち1万2000戸ほどが市有地への建設で、多くが市有地に建てることができた。
また、約37%が公園・スポーツ施設の大きな土地を活用して建てられた。

さらに、約3400戸が公団住宅(旧・日本住宅公団)の土地に建った。旧国鉄が持っていた土地を住宅に転用するために置いていた土地も使われた。どれも現在の沖縄にはない “ストック” だ。
それでも、よい条件ばかりではなかったという。
「神戸市だけで3万戸弱を建設したその半分が、六甲山の裏側にあたる郊外に開発中の住宅地で、生活利便性の問題で当選しても引っ越せない人が多かった。また埋め立て地、ポートアイランドなども合計で5000戸ほどあり、浸水被害が想定され、用地として難しいけれども建てざるを得なかった」

ハードとしての住宅の問題だけではない。災害で住み慣れた住宅や土地を失う喪失感は大きい。被災後の心のケアなど、考えておくべきことは多い。
「私は市町村の様々な計画を策定する委員会に入っているけれど、例えば公園整備計画などをやるときに、 “災害時に仮設住宅にする予定ですか?” と聞いたら「はぁ?」と言われる。そんなこと考えたこともなかったと。大規模災害が起こったときに仮設住宅に転用できる土地というのは普段から考えないと、本当に大変なことになる。今からやっておかないといけません」
過去の災害に学び、沖縄ではどれくらい仮設住宅を確保できるのか。あなたの生活圏ではどうだろうか。まずは想像してみてほしい。(話:防災士・社会福祉士 稲垣暁、構成:久田友也)
※本記事は稲垣暁さんが奥能登豪雨をテーマに話したRBC iラジオの情報番組「アップ‼」から構成したものです。(この記事の【前編】を読む)