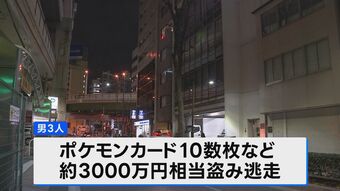非コンビニ事業の分離で株価は上がるのか
問題は、非コンビニ事業を分離、売却して、目論見通りに株価が上がるのか、です。最近は「コングロマリット・ディスカウント」という言葉が大流行です。多角化で非中核事業を多数保有していることが資本効率を妨げ、企業の潜在的な成長力を奪うことを通じて、株価が本来あるべき姿より過少に評価されるという現象です。
安易な事業領域の拡大を戒める言葉としては意味があるのでしょうが、巨額の赤字を垂れ流している場合を除けば、コングロマリットをやめさえすれば企業価値が上がるというほど、単純な話でもないでしょう。
コンビニ事業の成長力こそ問題の核心
10日発表されたセブン&アイの中間決算は営業利益が22%も減少しました。営業利益減少の7割は、インフレが直撃するアメリカのコンビニ事業の不振によるものです。次いで2割が、物価高の影響がジワリと出てきた国内コンビニ事業の低迷によるものでした。成熟期を迎えたコンビニ事業に、かつてのような革新性が見られず、インフレ時代への適応が遅れていることこそが、最大の課題のように見えます。その意味では非コンビニ事業の売却よりも、コンビニ事業の成長力こそが問題の核心と言えるでしょう。
社名からアイが消えて
セブン&アイという社名は、一般的にはセブン-イレブンのセブンと、イトーヨーカ堂のアイだと受け止められています。しかし、セブン&アイのホームページには、7つの事業領域と、イノベーションのアイ、愛のアイだと、説明されています。
いずれにせよ、社名がセブン-イレブン・コーポレーションに変更されれば、アイは社名から消えてなくなります。企業価値すなわち株価を上げろと、モノ言う株主に迫られた末に、買収まで仕掛けられている現経営陣には、非コンビニ事業の分離に進む以外、道がなかったのかもしれません。それでも、日本を代表する流通グループが、祖業に根差した「商いのDNA」や、消費者産業としての大きな「夢」を語らなくなるのであれば、寂しい限りです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)