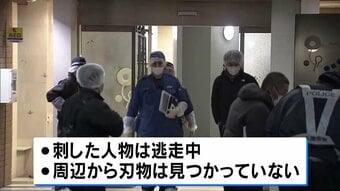お客様とはおたがいさま
一方で私は、これらの法や制度の策定だけでは、アンバランスな状況になりうることを懸念しています。具体的には、以下の3つの理由からです。
1つ目は消費者にとって、正当な主張を必要以上に抑え、本来カスハラなどしない顧客にとっても窮屈な消費行動の場になってしまう恐れがあること、2つ目が組織にとって、カスハラ対策を行うことが、顧客をけん制しているかのような後ろ暗さにつながってしまうこと、3つ目は従業員にとって、行き過ぎたカスハラ対策が、接客スキルや経験、モチベーションを制限してしまう可能性があることです。
ではどうすればいいのか?私は、カスハラが対人関係の問題を含んでいる以上、法や制度で規制するだけでは不十分で、もっとソフトの部分、おたがいが思いやりを持って譲歩し合ったり、よりよい関係性のためにおたがいが努力をする、といった部分が、必要だと思っています。カスハラは人と人との関係性が極めて重要な側面を持っています。だとすると、法や制度の整備と共に、よりよい顧客と従業員との関係性をめざしていくことが、なくてはならない側面だと思うのです。
望ましい関係性は、顧客と対応者とが対等であることです。ハラスメントは、社会的立場が高いと思っている者が、低いとみなしている相手にするもので、対等な関係では生まれません。平身低頭で接客をする従来の「お客様は神様」対応ではなく、あくまで対等に、顧客と従業員が接することができる、世間話ができるような関係。そして常にYesではなく時には毅然とした態度でNoと言える関係。でも譲歩できる可能なときは温かな思いやりを持っておたがいが接することのできる関係。今後望まれるよりよい顧客と従業員との関係はそんな「おたがいさま」の対等な関係だと思っています。
周りを見回すと、そこかしこにそんな対等な関係はあるはずです。遅延にイライラしていたけれど車掌さんの丁寧なアナウンスで「まぁ、しょうがないか」と思えたこと。コーヒーチェーンの店員さんとの他愛ない会話で、「今日も頑張ろう」と元気がもらえること。もたもたしているけど頑張っているコンビニの新米レジ担当者に、最初はイライラ、でもいつしか心の中で「頑張れ」と応援していたこと。
そこにあるのは、許容できる範囲をちょっとだけ増やした温かい消費者の眼差しと、たゆまない接客努力を続ける従業員の姿です。法や制度が整いつつある今、従業員、組織、消費者、それぞれが、できること、持つべき態度を意識し、努力し続けた時に、そんなおたがいさまの社会が実現されると信じています。
<執筆者略歴>
島田 恭子(しまだ・きょうこ)
予防医学者・保健学博士
一般社団法人ココロバランス研究所 代表理事
東洋大学 講師(非常勤)・研究員(客員)
専門は精神保健学(ポジティブ・メンタルへルス)、予防医学、ストレスマネジメント
企業での人材育成の経験から、人の心の健康・予防の重要性を感じ、東京大学大学院医学系研究科で、予防医学・メンタルへルスを研究。“メンタル未病”をキーワードに、医学や心理学の知見を、実社会に役立てる支援を行う。
とくにサービス業・対人援助職のストレスレベルが高いことに気づき、2021年に日本カスタマーハラスメント対応協会を設立。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版(TBSメディア総研が発行)で、テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。2024年6月、原則土曜日公開・配信のウィークリーマガジンにリニューアル。